【イベントレポート】Web3 Development MTG#9「Web3イベント大総括会 ~コミュニティはどう盛り上がり、どこに向かうのか?」2023.9.28
株式会社Ginco

イベント概要
株式会社Gincoでは、Web3の普及と発展に向けて、「Web3 Development MTG」というイベントを開催しています。第9回を迎えた今回は「Web3イベント大総括会 ~コミュニティはどう盛り上がり、どこに向かうのか?」を主題に、5つのWeb3イベントの主催者の方々が集い、それぞれイベントの後日談や所感、来年の構想をどういう思惑で進めていきたいかについて議論しました。弊社Ginco代表取締役副社長の房安 陽平がパネルディスカッションのモデレータを務めました。このイベントレポートではその概要をダイジェストしてお届けしたいと思います。
ご登壇者のご紹介
Ginco 房安氏: 皆様、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。まずはご自身のご紹介と主催されるイベントの概要についてお聞きしたいと思います。
B Dash 西田氏: B Dash Venturesの西田と申します。私は以前メディアで編集長を務め、その後2013年から今の会社に参画しディレクターを務めています。
B Dash Venturesは投資ファンドとして今年で12年目を迎える会社です。これまで主にインターネットビジネスに投資してきましたが、その経験を活かして「B Dash Camp」というイベントを開催していきました。インターネット業界の第一線で活躍する経営者などをお呼びする招待制カンファレンスとして、今年11月の開催で20回目を迎えます。
Web3との接点では、2018年から姉妹ファンドを立ち上げ投資活動を展開しています。昨年からクリプトに特化したイベント「B Dash Crypto」も開催し、業界振興に向けて取り組んでいます。
IVS Whiplus氏: こんにちは、Whiplusと申します。私は中国出身で、上海、カナダ、ニューヨーク、東京など8つの大学で学んできました。新卒で組織人事のコンサルティング会社に入社し、その後グローバルマーケティング責任者を務め人事イベントなどを主催してきました。
その後退職して、昨年渋谷の東急プラザで開催されたNFTアート展示会に出展したことを機にこの業界に参入しています。そこでIVSの方々とご縁を頂き、クリプトイベント「IVS Crypto」を主催する立場になりました。
去年のIVS Cryptoは沖縄の那覇で2,000人近くの方々にご参加いただきましたが、今年は京都で2回目の開催ながら約1万人の方々にお越し頂きました。
JBW 箭内氏: 初めまして、箭内と申します。私は20年以上デジタルエンターテイメントやマーケティングに関わり、起業も数回経験してきました。現在は株式会社みんとに所属しながらブロックチェーン関連イベントの運営に携わっています。
これまで6回のカンファレンスを主催してきましたが、昨年から「Japan Blockchain Week」として開催しています。今年は経済産業省やデジタル庁にも後援を頂き、さらなる日本のWeb3の推進に向けた基盤づくりを目指しています。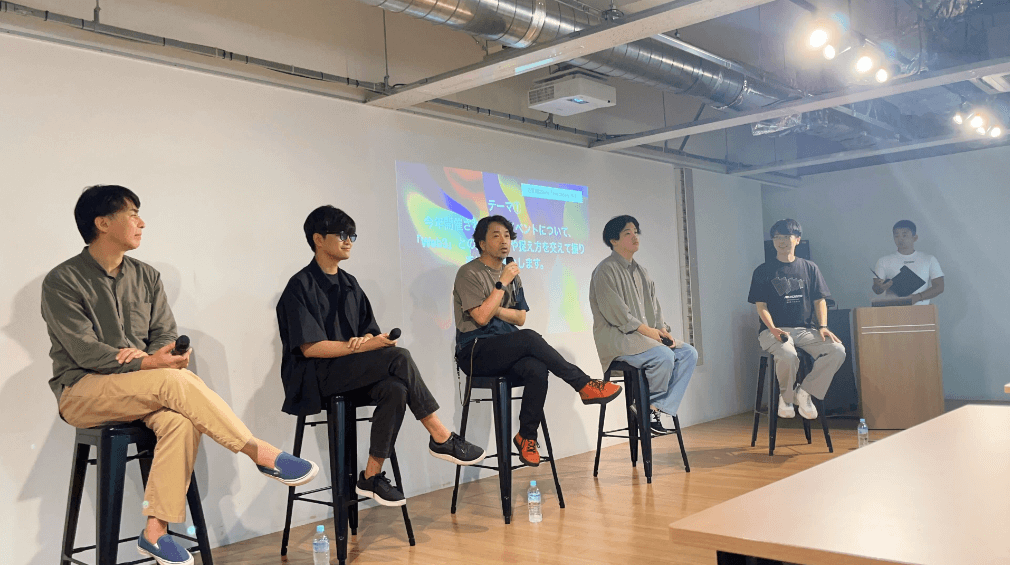
WebX 青木氏: 株式会社CoinPostで取締役・CSOを務めている青木です。CoinPostは暗号資産やブロックチェーン関連の記事を国内で最も大規模に発信しているメディアです。
WebXは今年初めて開催したWeb3イベントです。初回ながら金融庁や経済産業省、デジタル庁からご後援を受け、内閣総理大臣をはじめ政治家・官僚の方々も含め業界の著名人にご登壇いただきました。お陰様でイベントのユニークユーザー数は約9,200人、2日間で約1万6000人と多くの集客を得ることができました。
Ginco 房安氏: 本日モデレータを務める株式会社Gincoの房安と申します。弊社はウォレット関連事業以外にもブロックチェーン関連イベントを主催しています。本日のイベント「Web3 Dev MTG」は毎月か隔月という頻度で開催しております。
また、今年6月には「Web3 Future」という1日規模のイベントを八重洲でも開催しました。イベント規模は前述の皆様に比べ小さいですが、デジタル庁の平将明氏にも基調講演を頂き、企業のお客様を中心に会場を埋めることができました。
今日は、皆様との有意義な対話を通じて情報を共有させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
今年開催されたWeb3イベントについて、主催者側の狙いと実際の成果を振り返る
Ginco 房安氏: 今年様々なWeb3をテーマにしたイベントが開催されました。その中でも主催する側のこれまでの沿革や、ベンチャーキャピタル、メディアなど立場によってもイベントの内容が異なっていたかと思います。ご登壇者の皆様には自社が開催するイベントの特徴と、イベントを終えた手ごたえや感想を率直にお聞きしたいと思います。
IVS Whiplus氏: IVSは「Headline Japan」という日本・アジアを中心に国内外に展開するベンチャーキャピタルが運営しているカンファレンスです。昨年からWeb3領域に特化したイベント「IVS Crypto」も同時開催することになりました。
この「IVS Crypto」の開催で大切にしているコンセプトが2つあります。
1つは、新しい技術、人脈、知識、市場に焦点を当てて多くのコミュニティやパートナーを育成する場を提供すること。もう1つは、次世代のリーダーたちにスポットライトを当て、大企業の方々とベンチャーの若手起業家が同じ土俵に立ちアピールできる機会を提供することです。
これらをもとに、スタートアップ企業がベンチャーキャピタルと直接相談できるブースなども設営しながら特徴的なイベントが開催できました。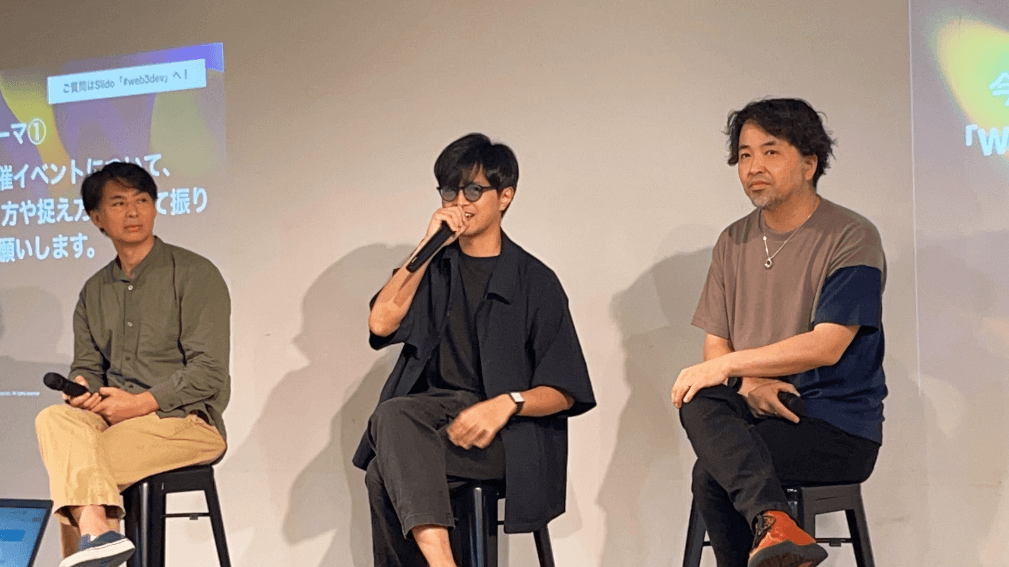
Ginco 房安氏: 昨年からWeb2イベントとWeb3イベントを同時に開催しているとのことですが、今年の「IVS Crypto KYOTO」では実際に参加された企業の比率はどのくらいだったのでしょうか。
IVS Whiplus氏: 昨年の「IVS Crypto NAHA」ではWeb2が「2」に対してWeb3が「1」という割合でしたが、今年はそれが「1:1」になりました。Web3の割合は着々と増えています。
Ginco 房安氏: ありがとうございます。続いて西田さんお願いいたします。
B Dash 西田氏: 「B Dash Camp」はIVSさんと同じようにベンチャーキャピタルが主催するイベントです。
我々は以前から参加企業を招待制にし、お互いに学び合いながらネットワーキングができる環境を提供する、というコンセプトを持ち続けてきました。昨年から始めたWeb3イベント「B Dash Crypto」もこの考えのもと開催しています。
我々の目的は、日本からWeb3起業家を多く輩出することです。そのため、イベントではスタートアップの起業家が投資家などに向けて自社の技術やサービスをアピールする、いわゆるピッチイベントを開催しています。ここでWeb3テクノロジーの専門知識を持つ方々と、ビジネスシーンで活躍する大企業の方々を結びつけてきました。
そして、もう1つの狙いは、Web2企業とWeb3企業との対話を促すことです。これまでのイベントを通して、Web2企業とWeb3企業はお互いに交わらない、という課題感を改めて感じたため、来年は新たな試みを考えています。
Ginco 房安氏: 私もこの「Web2企業とWeb3企業が交わらない」という感覚に共感するところがありますが、これにはどんな原因があるとお考えでしょうか。
B Dash 西田氏: 話題にする内容のレイヤーが異なることに原因があるように思います。Web2企業はサービス面を中心に話しますが、Web3企業はインフラ面も含めて話題に取り上げます。
例えば、トークンやNFT、IEO(イニシャル・エクスチェンジ・オファリング)などは比較的同じ理解度で会話が進められますが、DeFi(分散型金融)について語ろうとすると議論レイヤーの違いのためか意思疎通がしづらいように思いました。
Ginco 房安氏: なるほど、Web3というのはその点で特異な業界なのかもしれませんね。続いて、青木さんお願いします。
WebX 青木氏: 「WebX」は運営母体であるCoinPostが情報媒体であるため、B DashさんやIVSさんとは異なるコンセプトで企画されています。
これまで日本の暗号資産業界では情報格差が生まれていました。その原因は海外の英語で発信される一次情報を得ることができる人とそうでない人がいるからです。CoinPostはそのギャップを埋めるために、情報をいち早く日本語で届けることに取り組んできました。
今回開催した「WebX」も従来CoinPostが果たしてきた役割の延長線上にあるものです。海外では「Consensus」「Token2049」など有名カンファレンスがありますが、そのクオリティを国内で手軽に味わえる場を作りたいと思い開催に至りました。
また、これまで国内でポジティブなニュースがあるのに、それが海外に伝わらないわだかまりを感じていました。最近で言えば、LPS法と呼ばれる投資対象などを規制する法律の改正、法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の見直しなど、国内外にとってポジティブなニュースがあるにもかかわらず、それを海外に効果的に伝える手段が不足していました。
そこでWebXでは多くの政治家や行政の方々にご登壇頂き直接語って頂いたことで、日本の今を正しく伝えることができ、海外のメディアにも注目してもらえました。これが今回のイベントで我々が意図して大きな手ごたえを感じられた点でした。
Ginco 房安氏: まさに日本のプレゼンスを高めるイベントになりましたね。ありがとうございました。続いて、箭内さんお願いします。
JBW 箭内氏: 我々が開催する「Japan Blockchain Week」のコンセプトはシンプルに「ブロックチェーンを多くの方に身近に感じてもらおう」というものです。
ロサンゼルスや台湾など世界各国では「Blockchain Week」と名が付くイベントが開催されており、様々なイベントが特定の期間に集中的に実施されることで、多くの方が多様な切り口でブロックチェーンに触れる機会が生まれています。そのテイストを日本で手軽に味わってもらいたいと考えました。
先ほどWeb2とWeb3には隔たりがあるというお話がありましたが、我々の場合はその壁を感じさせないオープンさをウリにしています。そのためには、イベントのオーガナイザーはメインの教育的なコンテンツだけでなく、パーティのように交流が深められる場をトータルで企画してきました。
Web3イベントに根付くパーティ文化はどこから来たのか?なぜ必要なのか?
Ginco 房安氏: 多くの方から寄せられる質問の中に「なぜWeb3イベントはパーティばかりを開催しているのか?」というものがあり、私もよく尋ねられます。箭内さんはこのパーティの意義をどのようにお考えでしょうか。
JBW 箭内氏: 確かにパーティの開催はWeb3産業の特徴と言えそうです。
海外ではカンファレンスが終了すると、その場がパーティ会場に切り替わることも珍しくありません。日本でのイベントもその流れを汲んでいるかと思います。
しかし、ただパーティという場で交流を楽しむだけでなく、夜通しプロジェクトや業界の話題についてディスカッションする姿も見られています。
この様子はWeb3ビジネスがコミュニティ主体であることにも起因しているようにも思います。人と会話をして共同で開発をする習慣が、このパーティという場を結び付けたのかもしれません。
また個人的な意見になりますが、Web3業界は金融でありながらエンターテイメントの要素も帯びています。それゆえ詐欺師が多くいるのも事実です。そのため、パーティという直に出会える場を通して相手が信頼できるかどうかを確かめる、という点でも意味があるものと感じています。
B Dash 西田氏: 私はパーティがWeb3産業の協業・共創文化に直結していると思います。
Web3ビジネスが他の産業と大きく異なるのは、数社で協業する、という文化があることです。場合によっては競合する企業を巻き込むこともあり、この様子はWeb3以外の業界では信じられないことだ、と言われています。コミュニティの作り方がこれまでと違う点は非常に特徴的なことだと思います。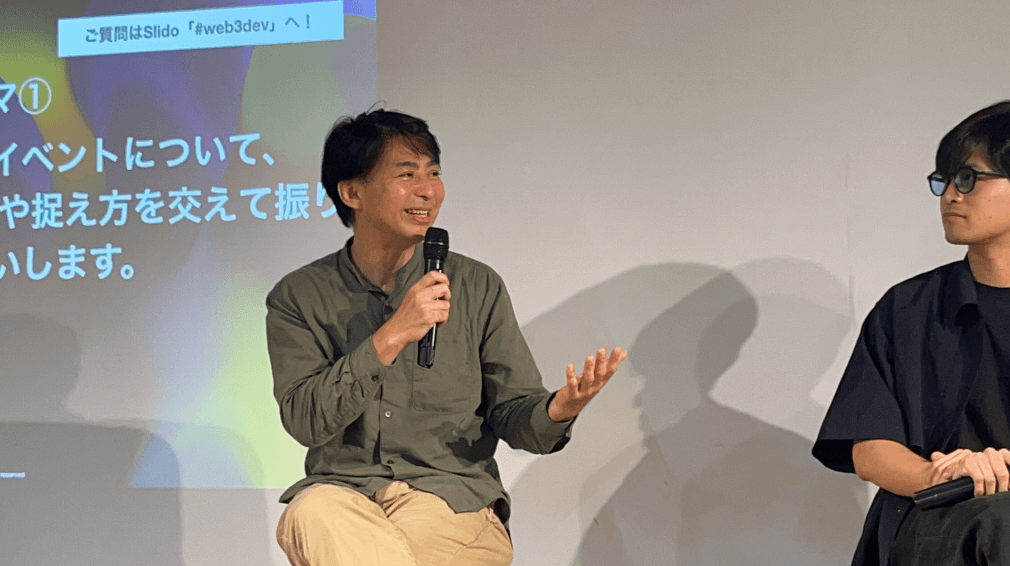
Ginco 房安氏: たしかにそうですね。Web2のベンチャーキャピタルの方がこのWeb3のスタンスに感動して、真似したいという声を聞きました。
IVS Whiplus氏: 同意です。相手がどんな経営者なのか、いち早く知るためには一緒に働いてみることが何より有効な手段だと思います。パーティはこうした「ビジネスマッチング」の第0フェーズとして、ビジネスパーソン同士が相手を知るきっかけになっています。
またイベントを主催する側としては、その場にいかに魅力的でポジティブなイメージを持たせるか、という視点でもパーティを重用します。
ベンチャーキャピタルの方々の究極的な目的は魅力的な出資先の発掘であり、そのためにイベント主催者は、多くの起業家・イノベーターがオープンにコミュニケーションできる彩り豊かな場を創出しようとしています。
Ginco 房安氏: パーティはWeb3においてコミュニケーションの媒介としての意義があったということですね。
「拡大路線?それとも密度重視?」主催者が目指すイベントの方向性と今後のビジョン
Ginco 房安氏: 今年Web3業界のイベントは規模を拡大させたものが多かったように思います。一方でイベントにクオリティを求めるアプローチもあったと思いますが、何が今年のイベントの方向性を決めたのでしょうか。
IVS Whiplus氏: IVSとしてはイベントの拡大を進めていますが、その理由は業界の見通しが明るいと考えているからです。
例えば「キャズム理論」によれば、新商品をマスアダプションさせるために乗り越えなければならない深い溝があると言われ、Web3は現在まさにその溝にあります。また、「ハイプサイクル」と呼ばれる技術の成熟、採用、適用の度合いを示す曲線によれば、Web3は幻滅期と呼ばれる谷にいます。
これら2つの指標だけを見ても、今後Web3は拡大するものと確信しています。昨今あらゆるものがブロックチェーンに保存される未来があちこちで語られていますので、IVSとして.comはこの潮流に乗り今後も拡大路線を進めていきたいと思っています。
ただ一方で、Web3プロジェクトと投資家とのマッチングの場については切り分けて、少人数でクオリティの高いコミュニケーションが取れる場を作っていきたいと思っています。
WebX 青木氏: WebXは2024年8月28日、29日に第2回目の開催を予定しています。そこに向けて今注力しているのは、さらなるコンテンツの強化です。
今年仕掛けたコンテンツでは「WebX」という名が示すようにWeb2とWeb3の垣根を超えたセッションを意識して企画してきました。例えば「スクウェア・エニックス ✖ STEPN」「経済産業省 ✖ Yuga Labs」など、これまでにない取り合わせで展開したことに注目が集まりました。
その成果を踏まえて、来年もクリプトメディアとしてWeb2からWeb3に多くの人を呼び込むためにさらにコンテンツに磨きをかけたいと思います。
JBW 箭内氏: JBWとしては来年も従来と同じ路線を進んでいく予定です。
ただ開催時期については様々なカンファレンスを1~2週間以内にまとめて実施してもよいのでは、と個人的には思っています。
今後、Web3イベントが拡大を続ければ、おのずと開催場所も限られてきます。例えば、東京ビッグサイト、それ以上になれば幕張メッセを検討する日も来るかと思います。このような大規模な場を選ぶことで、これまでこれらの大規模展示場を利用してきた多くのIT企業をWeb3・クリプト業界のイベントに呼び込みやすくなる、というメリットもあるかと思います。
また、イベントが多くなると参加者にとって足を運ぶ労力や金銭的な負担が増えてしまうため、そこに配慮することで多くの方に喜ばれるように思います。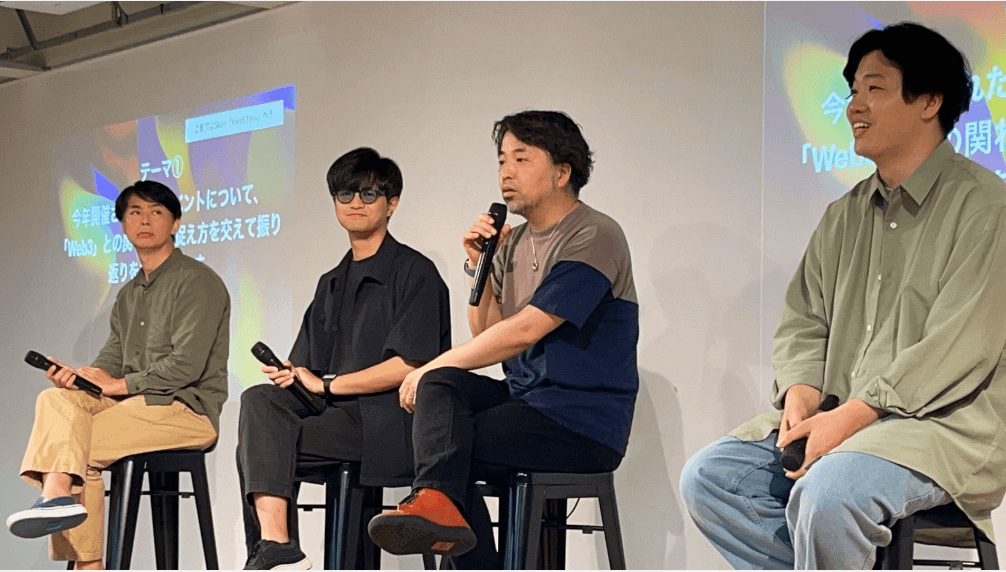
B Dash 西田氏: B Dashは先ほども触れましたが、来年はイベント規模を広げるよりも内容を工夫する方向で調整しています。その理由に、Web3のファウンダーの数が目立って増えていない背景が挙げられます。このまま同じ主旨のイベントを開催しても“同窓会”になりかねません。
現時点では未定ですが、来年はこれまで行ってきたピッチイベントを一度止めて、B Dash Cryptoと日程を分けたもう1つの招待制イベントを検討しています。これがビジネスマッチングのための新たな切り口になればと考えています。
IVS Whiplus氏: IVSも来年の展望について補足させてください。IVSは来年「IVS Global」という新設エリアを予定しています。ここにはWeb2、Web3に関わらず世界各国の企業が集まり、英語のみでやりとりする場を展開する予定です。
これは2025年に開催予定の「IVS OSAKA」に向けた準備として位置づけているものです。
Ginco 房安氏: 各社来年のビジョンについて触れてくださりありがとうございました。
今年のWeb3イベントで来場者数が1万人を超えたことで、日本におけるWeb3のプレゼンスが確実に高まっていると言えます。
最近行われた「東京ゲームショウ」が20万人規模であることを意識すると、この業界はまだまだ伸びしろが大きいことを改めて感じました。
以上、今回は2023年に開催されたWeb3カンファレンス主催者の方々をお呼びして、振り返りや業界の展望についてお聞きすることができました。今後発表される来年のイベント情報を楽しみに待ちたいと思います。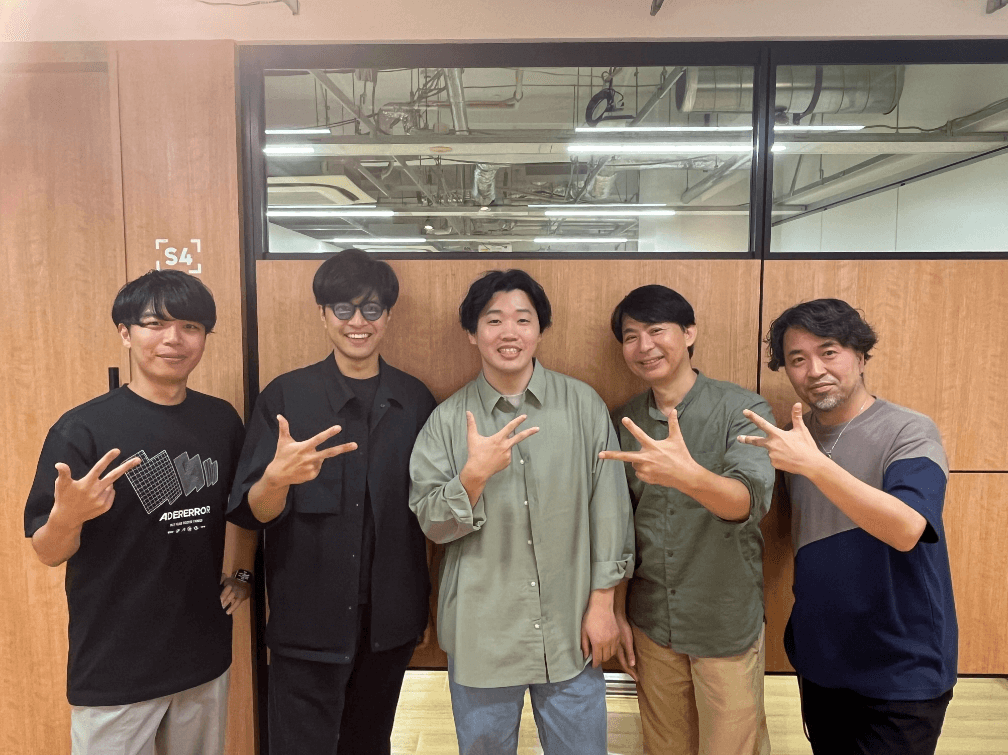
最後に
今回のWeb3 Development MTG Vol.9では、国内のWeb3イベント主催者の方々による貴重な議論をお聞きすることができました。
質疑応答でも「スポンサーの奪い合いはありましたか」「チケットの価格設定をどう考えているか」「具体的なビジネスマッチングの先行事例にはどのようなものがあったのか」など聞き応えのある内容が盛り沢山でした。ご興味があれば今後開催されるDEV MTGにも足を運んでみてください!
弊社Gincoでは、ブロックチェーンの活用を検討されている企業様向けにブロックチェーン導入支援・コンサルティングサービス等を行なっております。もし、セミナー参加者様、本レポートをご覧になった方で興味・ご関心がございましたら、下記の弊社概要欄よりお問い合わせください。