【イベントレポート】Web3 Development MTG#10「2024年に向けた緊急討論!金融、流通、ゲーム、エンタメ…ステーブルコインによるビジネス変革と課題」2023.12.11
株式会社Ginco

イベント概要
株式会社Gincoでは、Web3の普及と発展に向けて、「Web3 Development MTG」というイベントを開催しています。第10回を迎えた今回は「2024年に向けた緊急討論!金融、流通、ゲーム、エンタメ…ステーブルコインによるビジネス変革と課題」と題して、国内のステーブルコイン発行・流通に携わる3社にご参加いただき、最近のプレスリリースの背景や狙い、今後のユースケースをどう開発するか、について議論頂きました。モデレータにはCoinDesk JAPANの神本様をお迎えしております。このイベントレポートではその概要をダイジェストしてお届けしたいと思います。
ご登壇者のご紹介
神本氏: CoinDesk JAPANの神本です。本日はモデレータを務めさせて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。
弊社では暗号資産メディアとして、Web3、NFT、ゲーム、セキュリティトークンなどについて報じていますが、今回のテーマ「ステーブルコイン」についてデジタル資産の中でもキーファンクションになり得るもの、と非常に注目していました。
今年6月に改正資金決済法が施行されて以降は事業の開発段階に入ったことで、日々目まぐるしくステーブルコインに関する提携発表を耳にするようになりました。今日はその当事者の方々が登壇しているため、ここで直接聞きたいことをお聞きして情報をキャッチアップしたいと思います。
神本氏: では、自己紹介を簡単に一言ずつお願いします。
齊藤氏: 元信託銀行員で現在、Progmat代表を務める齊藤です。本日はステーブルコインが主題とのことで、関連する弊社のプラットホーム「Progmat Coin」をご紹介していきます。
近藤氏: SBI VCトレードの近藤です。私は新卒でSBIグループに入社し、4年半前からSBI VCトレードを担当、今年6月から同社代表を務めております。先日11月27日にSBIホールディングスがUSDCを発行するCircle社との業務提携を発表しました。その関連で本イベントに招集いただきました。
房安氏: 株式会社Gincoの房安です。GincoはWeb3インフラを提供する会社ですが、この度11月6日に齊藤さんのProgmatを活用してステーブルコイン「XJPY・XUSD」を発行する新規事業を発表しました。我々は銀行機能・信託銀行機能を持っていませんので、イシュアーとしてステーブルコインを発行することになります。こうした取り組みの狙いなどを今日はお話しさせて頂きます。
なぜステーブルコインに注目した?それぞれの背景や思惑とは何か
神本氏: まず最初に皆さんがステーブルコインに注目・検討し始めた経緯について教えてください。
齊藤氏: 当初はProgmatの祖業であるセキュリティトークン(デジタル証券)において、同時決済、いわゆるDvP決済実現のためのブロックチェーン上で決済完結が可能な手段を我々も必要としていました。ただ元々は決済領域まで自分たちでやるつもりは無く、外部のサービスとの連携(クロスチェーン)を前提としていました。しかし、結果として自分たちでステーブルコインを提供する方が早い、との判断に到ったものです。
その判断に到った経緯についてですが、前提として2021年の夏に、Progmatを使った日本発の不動産セキュリティトークンの発行を開始していました。前年の2020年にセキュリティトークンの規制法である改正金商法が施行され、金融庁としても”次のテーマ”としてステーブルコインの法整備を議論していたタイミングでした。
「トークン」というのは、信託という容れ物の中身に対する権利をブロックチェーン上で表象しているにすぎず、中身を不動産から法定通貨に置き換えてしまえば、セキュリティトークンの実績を活かしてステーブルコインができてしまうのではないか?というアイデアから金融庁と議論を開始した、というのが検討の直接的な契機になっています。
またパブリックブロックチェーンでの発行に到った経緯について、当初のターゲットはセキュリティトークンのDvP決済であり、セキュリティトークン発行基盤「Progmat ST」がコンソーシアムチェーンを用いていることから、ステーブルコインについてもコンソーシアムチェーンを念頭においた検討を行っておりました。2022年6月の改正資金決済法成立時点では、当局としてパブリックチェーンを念頭においた詳細な設計は未済であったのが実態でした。
その後、元々USDC等の既存のパブリックチェーン型ステーブルコインの国内導入に向けて活動されていたJCBA様と、自民党の先生方等を介して連携することとなり、2022年秋に急ピッチで”民間連合(銀行業界+暗号資産業界)”として「パーミッションレスステーブルコインワーキンググループ」を立ち上げ、同年12月に「中間報告」として具体的な提言にまとめて公表し、その数営業日に金融庁からもパブリックコメント募集の発信に到っています。
不特定者間使用が重要なステーブルコインにおいては、法的にも「可」となったパブリックブロックチェーン上で移転できることに利があると考え、「Progmat Coin」基盤では複数のパブリックブロックチェーンに対応する前提とし、まずはEthereumから活用しています。
現在の「Progmat Coin」基盤を用いたステーブルコインの用途については、最初期に想定していたセキュリティトークンの決済用途でのステーブルコイン活用は社会実装に時間を要することもあり、Gincoさんや様々な発行企画者の方々との取り組みが先行しています。
神本氏: 皆「Progmat Coin」の発表を聞いてそのような名前のステーブルコインが日本を席巻する、と想像していましたが、これは誤解とのことですね。
齊藤氏: はい、ネーミングのせいか、完全に誤解されてしまいました(笑)「Progmat Coin」はあくまで発行のためのプラットフォームです。
このプラットフォームを活用した「信託型スキーム」の最大の提供価値は、発行を依頼する人、つまりステーブルコインを使ったりサービスの中に取り入れたりする人(発行企画者)が金融ライセンスを取得しなくてもいい、という点にあります。
日本国内でステーブルコインを発行するには銀行業・資金移動業・信託業、いずれかのライセンスが必要なため、自前でステーブルコインを発行しようとすると膨大な負担が発生します。
他方、「信託型スキーム」の場合は、ライセンスを持つ信託銀行が”発行する器”として「Progmat Coin」基盤を使ってステーブルコインを発行し、発行企画者は信託銀行に指図するのみで実際に発行等を担う必要がないため、ライセンス取得等の負担がかかりません。
また「Progmat Coin」基盤で発行するステーブルコインは一律ではなく、各コイン別に”器(信託)”が独立して設定されるため、例えば「JPYC」、Gincoさんであれば「XJPY」などと、それぞれが決めたブランドネームを反映できます。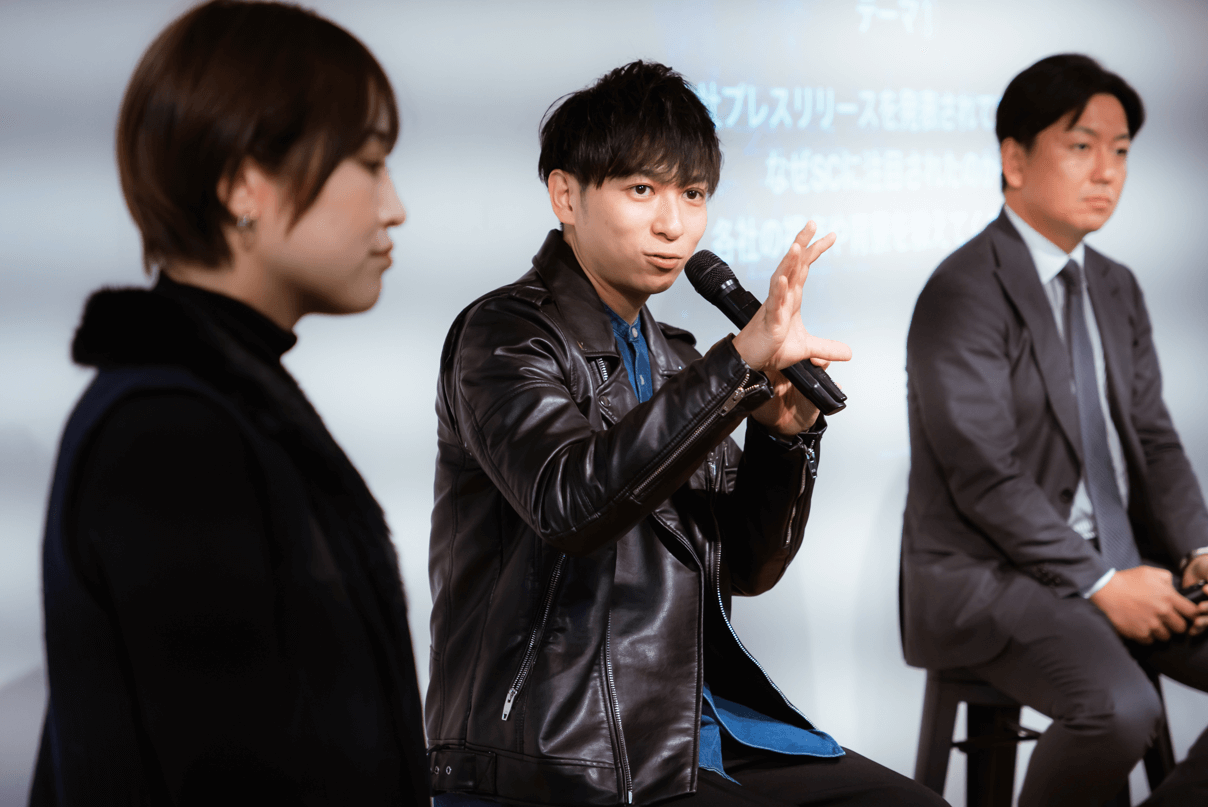
神本氏: 今の「Progmat Coin」基盤で発行されるステーブルコインは「信託型」と呼ばれるものだそうですね。それ以外のステーブルコイン発行方法「銀行預金型」「資金移動型」があるとのことですが、「Progmat Coin」基盤はこれらの型でも発行可能ということでしょうか?
齊藤氏: はい。私が信託銀行出身であることとは関係なく(笑)、「Progmat Coin」基盤としては、あらゆるスキームに対応するつもりです。現時点の規制を踏まえると「信託型スキーム」以上にメリットのあるスキームは現状ないと考えているため、まずは「信託型」から機能開発しています。
神本氏: ありがとうございました。続いて、そのProgmat Coinを活用するGincoさんの経緯や取り組み内容を教えてください。
房安氏: Gincoは日本円建てのステーブルコイン「XJPY」と、米ドル建てステーブルコイン「XUSD」の2銘柄を発行します。その目的は、国内の暗号資産交換業者や海外取引所との間での課題を解決することにあります。
元々Gincoは暗号資産取引所向けにウォレットやブロックチェーンインフラを提供するソリューションを提供してきました。一方で取引所にはウォレットを導入するだけでは解決できない課題もあると聞きました。
その1つが、取引所同士の決済です。取引所では取引の流動性を高めて効率良い取引を実現するために、日頃から他の取引所や流動性プロバイダー(以後「LP」と表記)と取引を行っています。
このような業者間の資金移動について、海外の取引所では米ドル建てのステーブルコインを活用していますが、国内ではこれまで円建てのステーブルコインが存在しなかったため、これら資金移動を銀行送金で対応してきました。
銀行送金と比べてステーブルコインの良さは即日着金でき手数料も抑えられる点で利点があるため、国内の取引所にもこのようなステーブルコインのニーズがある、と考えGincoが最初に切り込んだということです。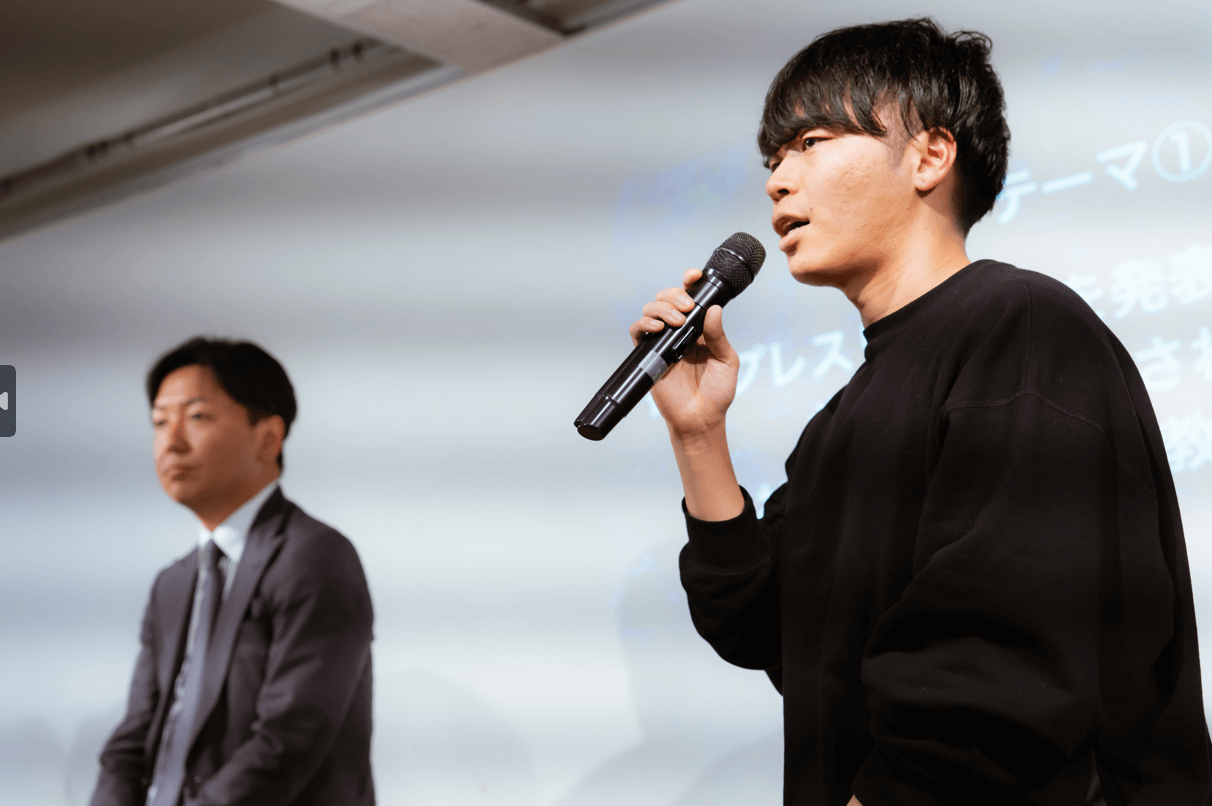
神本氏: 信託型ステーブルコインの発行でGincoさんは実際にどのようなことをしているのでしょうか?
房安氏: 発行依頼者はステーブルコインのブランド名やロゴを決めます。そしてそのステーブルコイン「XJPY」を扱ってくれる相手を開拓します。Progmat Coinを活用することでこれら業務に集中できます。
ただ、コインを扱う業者のKYCや不適切なところに流通した場合の対処などにも、Gincoとして関わるべき業務は伴います。最初はそのような負担を最小限に抑える意味でも「B to B」での用途に絞ることにしました。
神本氏: 今回はビットバンクさんやメルコインさんなども初期参加しているようですね。
房安氏: はい。明確に課題感を持たれていましたので先行参加頂きました。また、海外では米国最大手LPのカンバーランド・グローバルさんも参加しています。
神本氏: LPや取引所が参加するこの市場は、実際どのくらいの市場規模があるのですか?
房安氏: 月次で推定数千億円あるそうです。今後暗号資産市場の拡大が見込まれるため、月間単位で1兆円単位という数字も視野に入りそうです。
また、もう1つの米ドル建てステーブルコイン「XUSD」を活用すれば新たな市場開拓の可能性も広がります。現在「XUSD」はXJPY保有者の為替リスクをヘッジする用途を想定していますが、将来的にはこの2つのステーブルコインを使った通貨交換での用途も視野に入れています。
神本氏: ありがとうございました。初めてステーブルコインのわかりやすいユースケースが見えたような気がします。続いて近藤さんがステーブルコインに注目した背景と今の取り組みを教えてください。
近藤氏: 当社がステーブルコインに関心を持ったのは2023年6月の法改正がきっかけでした。
SBIグループは暗号資産やセキュリティトークンなどデジタル分野について全方位で積極的に参画しており、ステーブルコインへの参入も以前から検討してきました。
一方、Circle社も日本市場参入の意向があることを、7月頃のCoinDeskさんのインタビューを通して発表していていましたね。そしてこの度SBIグループとの発表に至りました。
Circle社が扱うステーブルコイン「USDC」は現在時価総額が約3.5兆円あり、すでに世界中の多くの人に信頼され使用されています。この提携では、USDCを日本の法規制に則って日本国内に流通させることが一番の目的となります。
神本氏: 海外ステーブルコインを扱うためにSBIは新たなライセンスを取得するのでしょうか?
近藤氏: はい、国内で海外のステーブルコインを扱うためには「電子決済手段等取引業」というライセンスが必要でその取得に動いています。プレスリリースでは、このライセンス承認を前提に「取り扱い開始」と発表させて頂きました。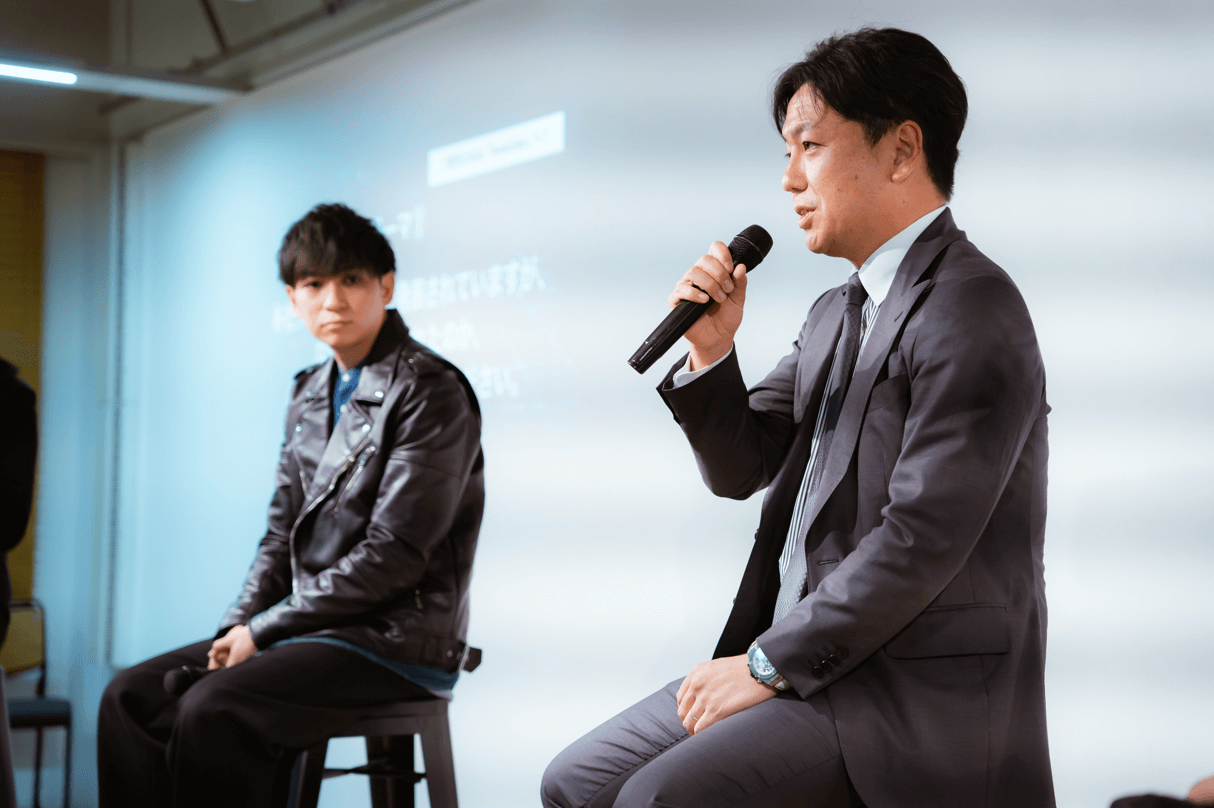
神本氏: 国内では電子決済手段等取引業をSBIさん以外にJPYCさんも取得予定とお聞きしています。このような業界に先駆けた取り組みは今後増加しそうですね。
ちなみに発表内容に「Circle社の銀行口座開設する」とありましたが、これはどういうことでしょうか?
近藤氏: 暗号資産に関連する企業は一般的に銀行口座を開設しづらい、という背景があります。Circle社のように海外業者となるとさらに国内銀行口座の開設はハードルが高くなります。
一方でSBIグループに新生銀行(現:SBI新生銀行)がジョインしたことで、今では暗号資産交換業・銀行・信託銀行全てを保有する国内唯一のグループです。
そのSBIグループとCircle社が提携することで、Circle社が銀行口座を開設し日本国内で決済を円滑に行えるようになります。USDCへのアクセスや流動性向上のためには、まずその基盤づくりが必要、ということでSBIがそれを支援していきます。
房安氏: 余談ですが、Gincoも2017年の開業当初、銀行口座の開設に苦労しました。また、日本市場に参入したい海外のLPも同様に、日本での銀行口座開設が難しく断念しているとも聞きました。
神本氏: ということは、海外企業が日本市場に参入するには、SBIさんのように銀行口座を支援してくれる企業とつながるか、もしくは、今後Gincoさんのようなステーブルコインを使ってウォレットでやり取りするか、ということになるのでしょうか?
近藤氏: そうですね、展開する事業によって海外企業もどのような手段を取るべきかを検討したり、日本のパートナーを探したりする必要があると思います。
実際にどう使われる?現在注目のステーブルコイン活用領域とは
神本氏: 今後どのようなステーブルコインの活用領域がありそうでしょうか?
齊藤氏: 今の日本では、自動販売機やコンビニでの決済にステーブルコインを使う、という用例は考えにくいです。なぜなら既存の電子マネー等でユーザーが満足しているからです。ステーブルコインに切り替えるスイッチコストの方が大きくなるような場合、変化は望めません。
また、地域振興券・地域通貨の発行、という用途もよく言及されがちです。しかし、すでに既存の特定のデータベースで集中管理するモデルで機能している事例もあり、それらのプロジェクトがわざわざパブリックチェーンで自由に移転可能な基盤に切り替える必然性があるかは、スイッチコストの観点では疑問符がつきます。
となると、パブリックチェーン上のステーブルコインはどこで活きるか。パブリックチェーンの一番の強みは「どこからでも、誰からでも、国に関係なくアクセスできる」という点にあります。その特徴を活用する場合、暗号資産やセキュリティトークン等のデジタルアセット取引以外の分野では、大きく2つ考えられます。
1つが、「クロスボーダー決済」の分野、もう1つは「プログラマビリティ」が求められる分野です。
まず「クロスボーダー決済」とは、別々の国の当事者間で行われる金融取引のことで、従来は金融機関やSWIFTを通して送金してきました。しかし、この種の取引は中間コストが高く、着金まで数日要することもあり不便でした。これをステーブルコインで代替することでアドレスさえあればいつでも誰とでも送れ、コストや時間も極小化できます。
もう1つの「プログラマビリティ」とは例えば、ある企業の会計処理をアプリケーション上で銀行と連携し、口座データを自動で書き換えて実行する、などを可能にする機能のことですが、近年このプログラマブルな機能が銀行には求められています。
そのために銀行は「更新系API」と呼ばれる機能を開放する必要がありますが、現在国内で更新系APIを提供する銀行は新興の数行しかなく、多くの銀行は勘定系システムに直接手を入れる負荷/コストの面からほぼ対応できていません。
そこで、ステーブルコインがその代替手段となって、条件さえ満たせば銀行の外部からでも自動的に送金処理を行えるようになります。
結論として、「クロスボーダー」と「プログラマビリティ」のどちらか、あるいは両方が求められる領域がステーブルコインである必然性が高い分野だ、と個人的には考えています。
房安氏: 私も「クロスボーダー」での用途が特に明るいと考えています。
Gincoが事業開発やコンサルティングを行う際にも、ステーブルコインについて関心を多く寄せられます。特に多いのが、貿易を行う企業や商社、貿易関連サービスを提供する企業様でした。
近藤氏: 私も同様にグローバルでの価値の移動がメインになると考えています。
USDCの場合、世界中のほぼどこでも安定的に米ドルと交換できます。その利点を活かせば今後新たなユースケースはいくらでも作ることができます。
ただし、USDCのような海外ステーブルコインについては現在の日本の法律では「保有上限額、一度の送金上限額が100万円まで」という制約があります。
そうなると、個人での利用が中心になりそうですが、直近お話させていただいた企業が検討されているユースケースで、海外拠点における「社員の出張費の処理」や「拠点間での資金移動」などでの用途も考えられるのではとのことでした。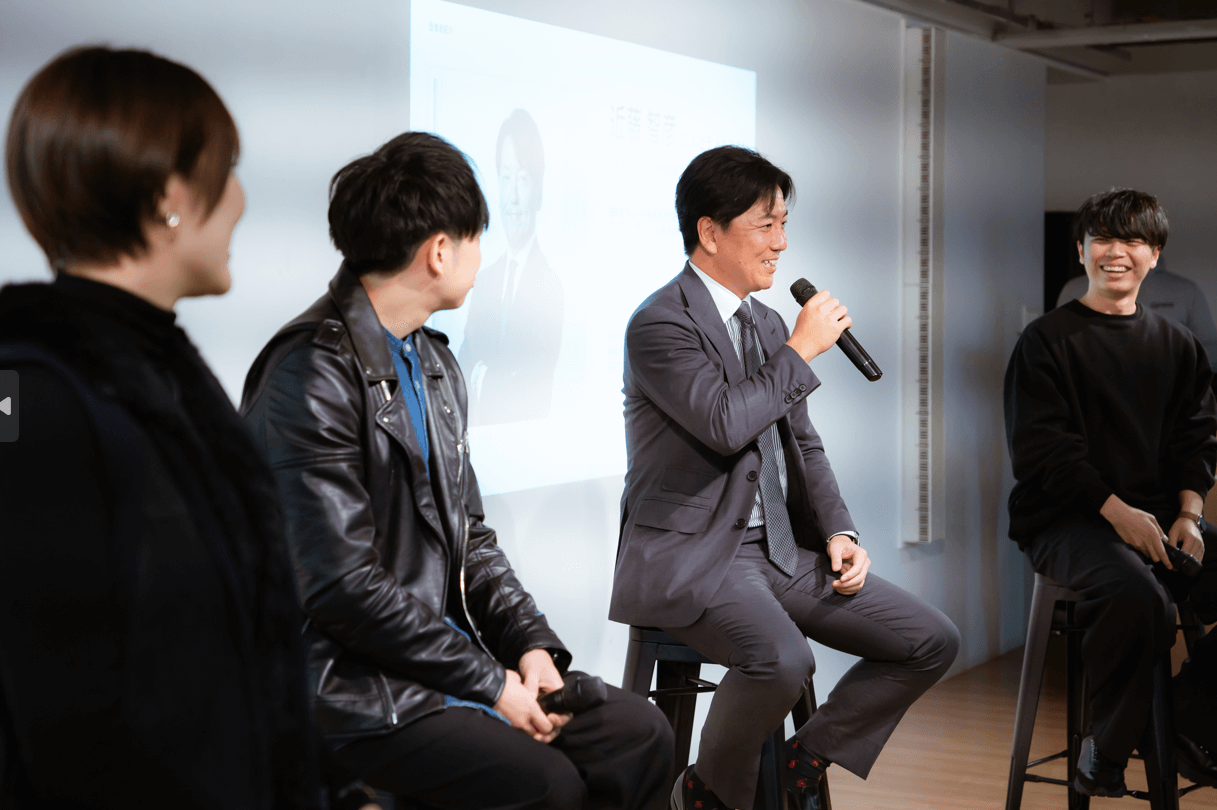
今後、事業者がステーブルコイン活用を検討する場合、抑えるべきポイントはどこ?
神本氏: では最後に、今後事業者がステーブルコインを活用する際に抑えるべき視点を共有してもらえますか?
房安氏: 今のところ日本では諸外国に比べてステーブルコインのビジネスモデルを作りづらいと言われているようです。
これは、諸外国と違い日本ではステーブルコインの原資となる預かり資金を運用にまわして利回りを得ることができないからです。
諸外国ではステーブルコインを扱う業者は、預かった資金を運用して金利を得ることができます。そして、その利回り分をキャンペーンの原資にすることで自社の新たなビジネスに活用できます。こうした手が打てませんので、C向けのステーブルコインはビジネスを実現しにくい傾向にあります。
一方、GincoはB向けのウォレットを自社で開発し、暗号資産交換業者らに提供するサービスベンダーです。そのため、使い勝手のよいステーブルコインがあれば、それを扱うB向けウォレットの提供価値が向上する、という相乗効果が「XJPY」や「XUSD」の発行目的であり、ある種のマーケティングツールとも考えることができます。
ただ、ステーブルコインの一番のメリットは、24時間365日ブロックチェーン上でいつでも移転できるところです。
この利点を活かして既存事業と相乗効果を生み出せる分野は、法律が整備されたばかりの日本では始まったばかりの取り組みです。新たなステーブルコインのユースケースを多様なステークホルダーと一緒に開拓したいと考えています。
近藤氏: USDC活用について言えば、抑えるべきポイントは先ほども触れた「保有と送金の上限額100万円」に尽きます。
この上限については個人での利用であればあまり支障はないのかと思います。また企業が使う場合でも、海外の送金先がUSDCを換金・利用できる場所なら、用途について制限されることはありません。取引先相手への支払いなど様々なユースケースを作れるかと思います。
齊藤氏: 「信託型ステーブルコイン」と、将来的に実現可能性がなくはない「預金型ステーブルコイン(電子決済手段)」においては、100万円という金額制限はなく大口取引で使えます。
注意すべき点は、発行した後の移転の容易性にあると思います。現状世の中の99%の事業者/個人がパブリックブロックチェーン上のアセットに直接アクセスしているわけではないため、それをつなぐ中間のレイヤーとなる「ウォレット」「ゲートウェイ」が重要になります。
しかし、Progmatではこの分野に参画する予定はありません。その理由は、それぞれの業界や事業者/個人毎にアクセスしやすいウォレットやゲートウェイは絶対に異なるからです。すでに昨年から様々な業者がウォレットへの参入を発表しており、この分野で1社が全ユースケースを独占することは想像しづらいですし、望ましいとも思いません。
例えば、銀行のチャネルや暗号資産交換業のチャネルでもその仕様は異なりますし、業界のエコシステムによって、あるいは使う側が望むアクセスポイントによっても異なるものです。
よってステーブルコインの活用を検討する立場にとっては、どんなウォレットやゲートウェイを作るのか、あるいは使うのか、が重要になりそうです。
神本氏: 本日はありがとうございました。
今回のセッションでは、国内のステーブルコインにおいて「クロスボーダー」がキーワードの1つになる、そして、ステーブルコインのユースケース開発はまだこれからだ、ということが見えてきました。ご参加くださった皆様、パネリストの皆様ありがとうございました。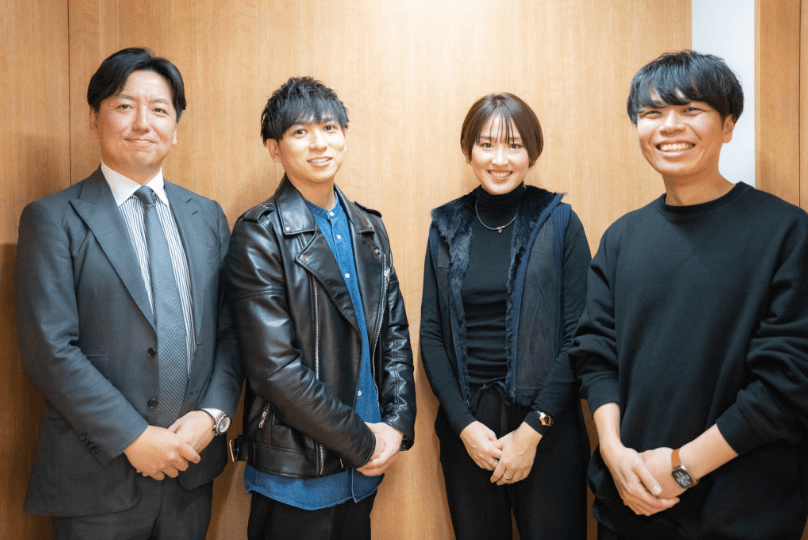
株式会社Gincoについて
Gincoは、「経済のめぐりを変えていく」をビジョンに掲げ、ブロックチェーン技術を活用し、企業のWeb3事業を支援するWeb3 Development Companyです。エンタープライズ向けにより早く、より安全に、より費用対効果が高いブロックチェーン活用を実現するインフラを提供しています。特にウォレットやノードの分野で国内トップの提供実績を誇ります。
所在地:〒104−0032 東京都中央区八丁堀三丁目27-4
代表者:森川夢佑斗
設 立:2017年12月21日
事業内容:クラウド型ブロックチェーンインフラおよび、同インフラを利用した各種エンタープライズサービスの開発・運営・提供
企業URL:https://ginco.co.jp/