【イベントレポート】Fintech協会主催・九州工業大学特別講演『ブロックチェーンの原点に立ち返る Web3はユニバーサルなインフラにならない?』パネルディスカッション 2023.10.25
株式会社Ginco

はじめに
2023年10月25日にFintech協会との連携により、九州工業大学の60名以上の学生エンジニアの皆様に向けたオンライン講義を開催させていただきました。当日、前半は弊社代表・森川が「ブロックチェーンとは何か」「Web3によって世の中がどう変わるか」についての講演、後半は同協会理事の河合氏・三輪氏と弊社代表の森川の3名でパネルディスカッションを行いました。今回はそのディスカッションパートをイベントレポートとしてお届けいたします。ブロックチェーンやWeb3に関して、また新たな切り口で議論が展開されています。この業界に興味がある学生の方、トークンエコノミーに携わる方々にご観覧いただければ幸いです。
パネリストの紹介
河合氏: 自己紹介を改めてさせていただきます。河合祐子と申します。私はもともと日本銀行出身でフィンテックセンター長を経て、今は本業としては高知銀行という地銀に勤めております。その傍らでFintech協会での理事等ブロックチェーン・Web3の研究者として関わっております。本日はモデレータを務めさせていただきます。
三輪氏: 三輪純平といいます。私は長い間金融庁に在籍し、フィンテック室の室長を務めていました。ブロックチェーンには早期から深い関わりを持っていたこともあり、現在は国際業界団体BGINを立ち上げて主にここで活動をしております。また大学で教鞭もとっています。BGINでは河合さんともご一緒しております。本日はよろしくお願いいたします。
森川氏: 株式会社Ginco取締役代表の森川夢佑斗です。弊社は国内で主に企業向けの暗号資産ウォレットやインフラを提供する会社です。本日は日頃からFintech協会と連携しているご縁から、前半では皆様の前で講義をさせていただきました。後半のパネルディスカッションもどうぞよろしくお願いいたします。
目次
Web3の定義とは?Web3で実現したい世界とは?
ブロックチェーン技術がユニバーサルになる世の中が来ると思うか。全員がアダプトしなければどんな世界になるのか。
ブロックチェーン・トークンエコノミーの理解者をもっと増やすべきか。そのためには何が必要か。
この世界に興味をもったら、何から勉強すればよいか
Web3の定義とは?Web3で実現したい世界とは?
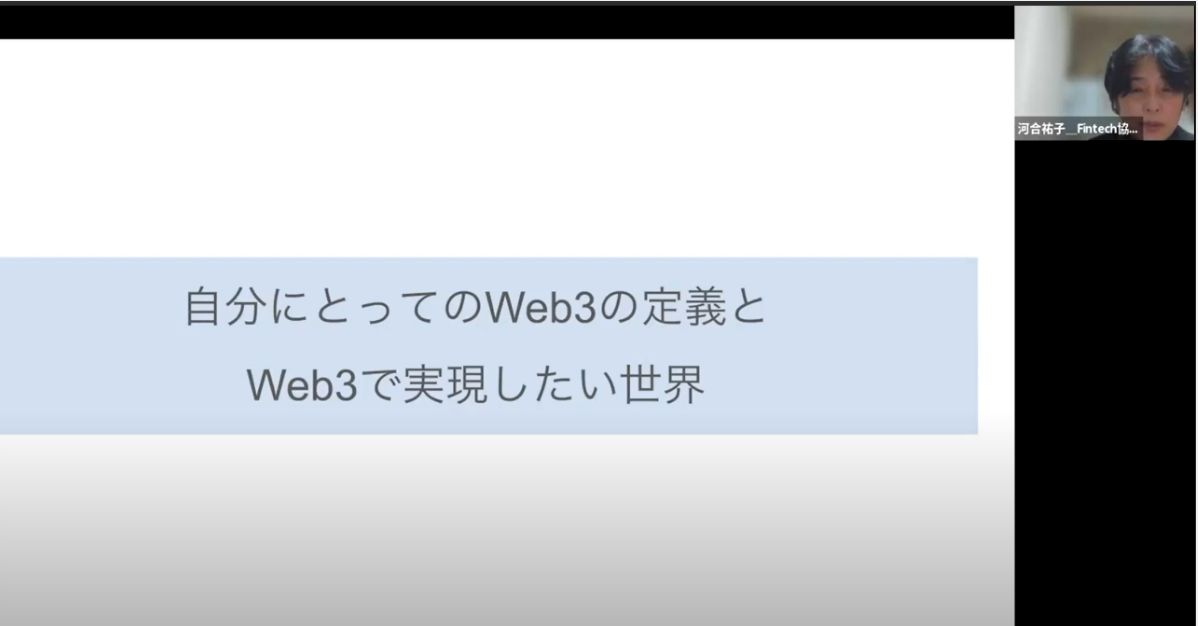
河合氏: Web1、Web2、Web3という概念は本日の森川さんの講義でも説明されていました。しかし「Web3」という言葉は人によって解釈が異なると言われています。それぞれの捉え方を改めて確認した上で、それぞれの目指すものを語っていければと思います。
三輪氏: 私はWeb3を、権利を自分たちに取り戻すための運動だ、と捉えているところがあります。喩えるなら「レコンキスタ(国土回復運動)」のようなものとも言えるかもしれません。
これまでWeb2と言われる時代の過渡期では、GAFAなどのビッグテックによってユーザーのプライバシーデータが占有されてきました。しかし、そのタイミングで登場したWeb3は、個人のアイデンティティに関わる情報をどう使うかを、自分自身が決められる。そういう意味合いを帯びています。
また、個人がつくった著作物についての所有権も、本人ではなく企業やプラットフォームが権利を主張し搾取されることもあります。それら権利をテクノロジーによって本来所有する人の元に取り返すことができるとも言われます。
Web3はある種の社会運動のような捉え方ができる、と私は思っています。
河合氏: このWeb3という新しいフレームワークによって、三輪さんが実現したいビジョンや夢にはどのようなものがありますか。
三輪氏: Web3がもたらすものの1つに「トークンエコノミー」がありますが、トークンという新たなタイプのお金が流通可能になったことに伴い、これまでにない経済圏が誕生するだろうと言われています。これを世の中にとって役立つ方向で実現したいと思い、私はその可能性に期待をしています。
ただし、このトークンには現状まだ安全性が確立されていません。例えばそのトークンの取引を記録する分散型台帳の管理にも課題を抱えているのが実のところです。
河合氏: お金の信頼がまだ十分に担保されていない、ということでしょうか。
三輪氏: そうですね。今までは日本銀行の信用によって日本円の価値が担保されていました。しかし、日銀のような後ろ盾がない通貨を人々はどうやって信頼することができるのか。
実際に人々がお金のどこに信頼を置くか、そのポイントは人によって異なるようです。例えばゲームの世界のお金をトークンにしたことでプレイヤー同士で交換がはじまったとします。それがいつの間にか信用力を持ち、やがて地方・地域に発展して新たな経済カテゴリーを作るかもしれません。
しかし、それと同時にこのトークンには「恐ろしさ」もあります。
トークンが普及した先に、これまで維持されてきた社会秩序が崩れることもあり得ます。不正利用の温床になることもあるためそこには規制が必要だ、ということも金融庁に勤めていた立場としては考えなければいけません。
この点も含めてトークンエコノミーには安全性が十分に配慮された環境整備が不可欠です。
河合氏: そうですね。Web3がこれまでと大きく異なる点は、中央銀行が中心となってきた通貨発行の役割が分散化されていくかもしれない、という点だと思います。今までの常識を覆すものにもなり得るため、信用についての議論はますます重要になりそうですね。
続いて、森川さんにも改めてWeb3の定義や今後の世界についてお聞きしたいと思います。
森川氏: 私は先ほどの講義ではWeb3を「ブロックチェーンを基盤としたトークンやデジタルアセットと今のWebサービスを、組み合わせることでもたらされる新しいサービスや体験だ」と定義しました。
こうしたデジタルアセットを活用した新しいサービスは、これまで資本主義的価値観の中で評価されづらかった社会意義のあるものに対して、価値を見直してそれをトークンとして還元できるようになるきっかけになるのではないか。
また、これまでSNSなど含めプラットフォーマーへの好意的な振る舞いが忖度されることが近年問題視されていますが、トークンを使うことで個人の活動を公平に評価・還元する1つの手段になるのではないか。
既存のWebサービスへのアンチテーゼになる、という期待をWeb3に寄せています。
ブロックチェーン技術がユニバーサルになる世の中が来ると思うか?全員がアダプトしなければどんな世界になるのか?
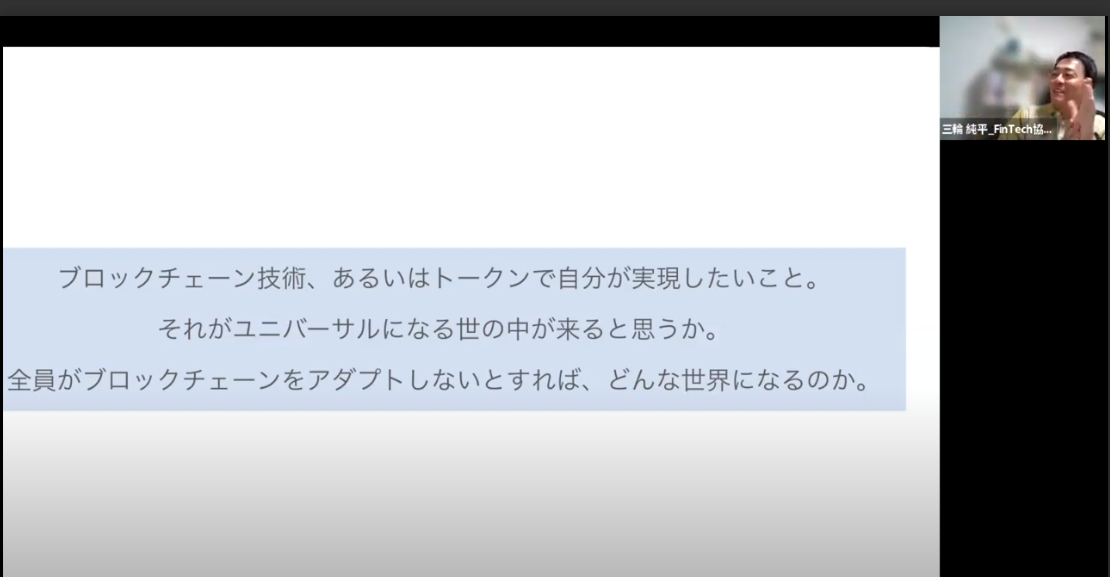
河合氏: 今後の世の中では、全員がWeb3を受け入れるようになるのか。あるいはそうではなく、Web2やWeb3が入り混じるようになるのか。
森川さんはどのような見立てを持っていますか。
森川氏: 私は、個人的な考えとしてもビジネス的な立場としても、全員がWeb3にアダプトする世界が来る、と予想しています。
しかしそれは少なくとも今日のように「マスアダプションするかどうか」を議論するうちは実現しないと見ています。
今なおトークンやブロックチェーンについて活発に議論が行われていますが、これらがやがて話題にもならなくなり、スマートフォンや我々の体験の中に摩擦なく融け込んでいる状態になっているかどうかが、それを測る1つの指標と言えるかもしれません。
これまで人々が携帯電話からスマホへと移行したように、Web3も一度回り出した歯車は止まることはないところまで来たと思います。ただ、今我々が認識している以上の世界が待っているように思います。
三輪氏: Web3がマスアダプションするかどうか、はブロックチェーンを事業として営む側にとって大きいことです。しかし、それを判断するのは我々のようなブロックチェーンを推進する立場ではなく、それを受け入れる側のユーザーや個人になるかと思います。
また、私は全員がブロックチェーンにアダプトすることはあり得ないと見ています。
その理由は、現在すでに様々な国の通貨があり、それぞれの通貨が通用するコミュニティが存在しているからです。しかも先ほども触れた通り、何をもって通貨を信用するかは人それぞれの思想が関係します。そうなると、すべての価値あるものがブロックチェーンを使ったものに置き換わる、と考えるのは無理があるようにも思います。
河合氏: となると、Web2の思想を持つコミュニティとWeb3の思想を持つコミュニティが混在するということでしょうかね。
ブロックチェーンは世の中のユニバーサルなインフラになるものだ、と期待する人もいますが、現状はまだトークン同士がシームレスに繋がっているわけではありません。
ましてや、ブロックチェーンには種類がたくさんありそれぞれに思想があるため、思想が異なるブロックチェーンに人々がそれぞれアダプトする、という方向性で進むこともあるかもしれません。
我々がWeb3と定義していた世界にもWeb2的なコンセプトが浮遊しているようですね。
ブロックチェーン・トークンエコノミーの理解者をもっと増やすべきか?そのためには何が必要か?
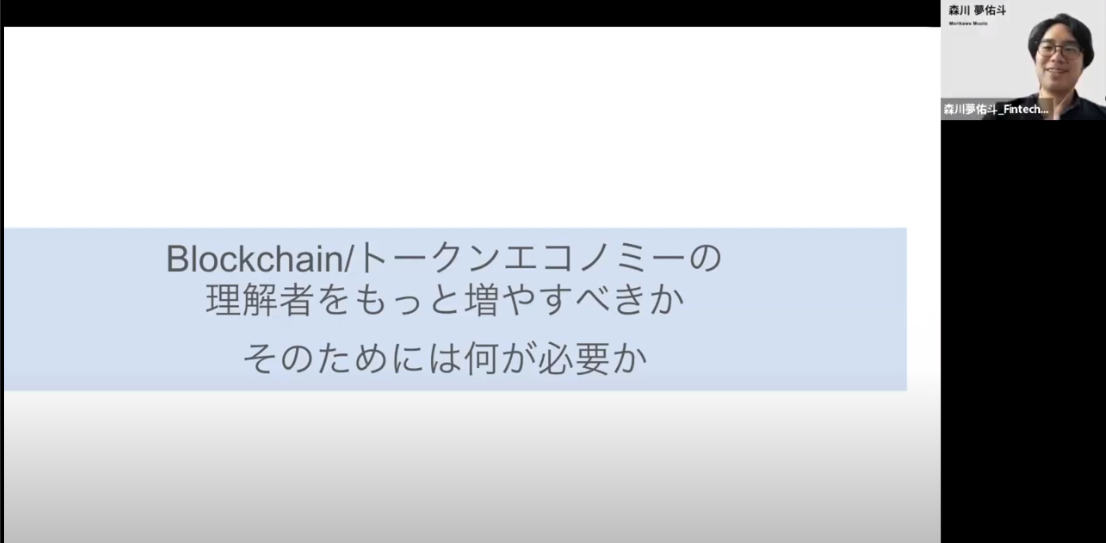
河合氏: とはいえ、ブロックチェーン技術やWeb3に期待するものがあります。その実現に向けて我々は理解者を増やすべきなのでしょうか。
三輪氏: トークンエコノミーは、真に必要だと思えた人、共感できた人の間で使えばよいものだ、と私は思っています。
なぜなら、ビットコインの成り立ちを知ってその画期的な仕組みに触れて心地よいものだと受け入れる人もいますが、そういった人が全てではないからです。
現に、この自己主権の通貨を「厳しい世界」と捉える人もいます。ならば金融教育が広まればよい、と言われますが、それを求めていない人にとってはお節介になる可能性があります。
河合氏: それを聞いて、私はサトシ・ナカモト氏が書いたと言われるビットコインのホワイトペーパーを連想しました。
このホワイトペーパーには、ビットコインを法定通貨と取引する、という記述はありませんでした。
ビットコインが世の中に広まった最たる要因は、ある種の「気持ちよさ」に共感が集まったからだと私は思っています。
例えば、従来アメリカから日本に国際送金をしようとすると、煩雑な手続きを経る必要がありました。しかし、ビットコインを使えば、ウォレット間で移動するというわずかな手間と時間でそれが代替できるようになった。これは何かから解き放たれたかのようなインパクトを与えました。
しかし、その後ビットコインの希少価値に注目が集まり、その取引が活発に行われるようになったことで当初のコンセプトとズレてきたのではないか、と私は考えています。
ひいては、ビットコインはその価値を信じ、自由に使い合うことで気持ちよさを知る者同士で使うものであって、大衆に使われるためのものではなかったのではないか、とも思えてきます。
一度このような「気持ちよさ」というものに立ち返ることで理解者が増えていくのかもしれません。
これについて、森川さんはどうお考えでしょうか。
森川氏: 理解者を増やすべきか否かについては、増えるに越したことはありません。しかし、理解者を増やすことが必ずしもマスアダプションに繋がるものではないとも思っています。
また、理解者が増えるにつれてビットコインを様々な使い方をしようとする発想が生まれるのは自然なことだと思います。それはブロックチェーンに限らず、AI、VR、メタバースなどの技術でも同じことが言えるのではないでしょうか。
そして、技術は理解されないと使われないのか、と言われるとそうとも限りません。近年ChatGPTを利用する人たちが、必ずしもAIという技術を理解して使っていない、ということがその証とも言えます。
よって、テクノロジーについての理解者を増やすよりも、「推進者」が増えることがマスアダプションに繋がるものと見ています。
ただし、新しいテクノロジーの推進者には、長期的な視点で社会に還元していくことが求められる、と私は思っています。そのためにはテクノロジーに対する好奇心、探究心を持つ人の方が適性があるため、我々がエンジニアを採用する際にはそこを重視しています。
河合氏: なるほど、技術の普及には理解者よりも推進者が必要ということですね。
先ほど触れられたChatGPTほど短期間で世の中に広まったツールはないと聞きます。ChatGPTがなぜこんなに広く世間に知られもてはやされるようになったのか。AIの第一人者である東京大学の松尾豊先生が「言語を扱っているから」と説明していました。
人間は年を重ねるほど言語力は豊かになると言われ、言語は年配層にとって得意分野でもあった。ChatGPTはその言語を扱う幅広い年齢層にとって用途が分かりやすいツールであったことが爆発的な普及の要因だった、と分析されています。
ブロックチェーンやトークンエコノミーにおいても、分かりやすい用途が生まれることが推進者を増やすカギになるのではないでしょうか。
森川さんはどのようなユースケースをそれに該当するとお考えでしょうか。
森川氏: ChatGPTほどの爆発力はないかもしれませんが、回答の一例として、NFTを使ったふるさと納税、が挙げられます。年齢を重ねるごとに増えるものは言語力だけでなく税金もです。ということで、お得感が伝わりやすいこれらのユースケースは広まりやすそうです。
河合氏: とても分かりやすいですね。
私は今年三輪さんとBGINの活動でスイスを訪れた際に「SBT(ソウルバウンドトークン)」が大きな注目を集め、有力なユースケースになる手応えを感じました。
SBTというのは、いわゆるウォレットから移動ができないタイプのNFTを言いますが、例えばこれを大学の卒業証明書として活用する事例が示されました。個人のアイデンティティに関わるものをウォレットに刻み込むことができたのは、とても印象的でした。
三輪さんは、他にも分かりやすいユースケースは思い当たりますか。
三輪氏: そうですね。亡くなったペットをアバターにしてトークンとして表現する、という世界観は受け入れられやすいかもしれません。
また、ユースケースの話から少し逸脱するかもしれませんが、貨幣とトークンの類似性に注目しています。
歴史をさかのぼると、貨幣は人間同士のコミュニケーションに一役買ったツールだったと言われています。王様や領主が交代すると流通する貨幣もそのたびに変わってきましたが、それでも貨幣は無価値になることはありませんでした。ローマ帝国が滅びても、貨幣だけは別のところでやり取りされ、コインの真贋がはっきりしない中でもそれが人間を結び付けてきたと聞きます。
だとすると、現代のトークンは貨幣の果たしてきた役割を踏襲できるかどうか、個人的に注目しています。
河合氏: 面白いですね。ブロックチェーン技術によってトークンには情報を刻み込んで保存できますね。これが何かしらのコミュニケーションツールになれば、トークンの面白さが広まる要素になるかもしれません。
この世界に興味をもったら、何から勉強すればよいか?
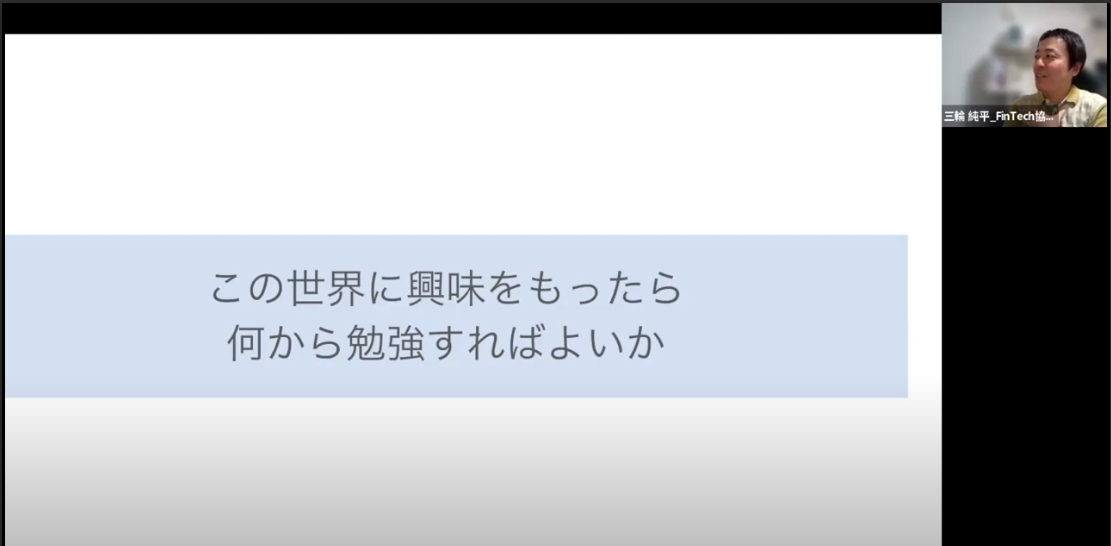
河合氏: 最後の質問です。本日のお話でブロックチェーンやトークンエコノミーに興味を持った学生の方がいた場合、どのような方法で学びを深めればよいでしょうか。お薦めするものはありますか。
森川氏: ブロックチェーンやWeb3をただ掴みに行こうとしても、コンテキストやストーリーを知らなければ、本当の意味で興味を持ちづらいかもしれません。
例えば先ほどの三輪さんのお話のように、貨幣の成り立ちや信用がどう生まれてきたのか、について併せて理解を深めるような人は、この業界を長期的な視点で見ています。
また、ブロックチェーンはAIなど他技術とも深く関わる技術ですし、1つの「点」で見るよりも「線」で捉えることをお薦めします。
三輪氏: 繰り返しになりますが、ブロックチェーンがもたらした革新性の1つは、「誰でもお金に似たトークンが作れるようになったこと」です。
それによってICOを使った詐欺が多く発生したことも事実ですが、これまで日銀が発行する日本円しか扱ってこなかった時代から考えると、別のお金があること自体が画期的な出来事です。
我々が今まで大学で教わってきた「マクロ経済学」というのは、中央銀行による管理通貨制度を前提に理論化したものです。しかし、トークンの登場によって発行体がますます増える今後において、これまでの経済学の常識は通用しません。学問を覆すことになることからも、大きな時代の転換期にいることが分かります。
河合氏: 「そもそもお金とは何か」という貨幣論から学ぶということが1つのアプローチということですね。
三輪さんも森川さん、御二方ともコンテキストから技術へ、というアプローチだったようですが、私は実際に技術に触れてみたことで、コンテキストを深めていった立場でした。
コンテキストから入り技術に興味を持つ人もいれば、技術から入りコンテキストを深める人もいるようですね。
コンテキストを深める際には、貨幣の歴史を学ぶことができる日銀の貨幣博物館、今回取り上げたサトシナカモトのホワイトペーパーが参考になるので、それをお薦めしてこのディスカッションを終えたいと思います。