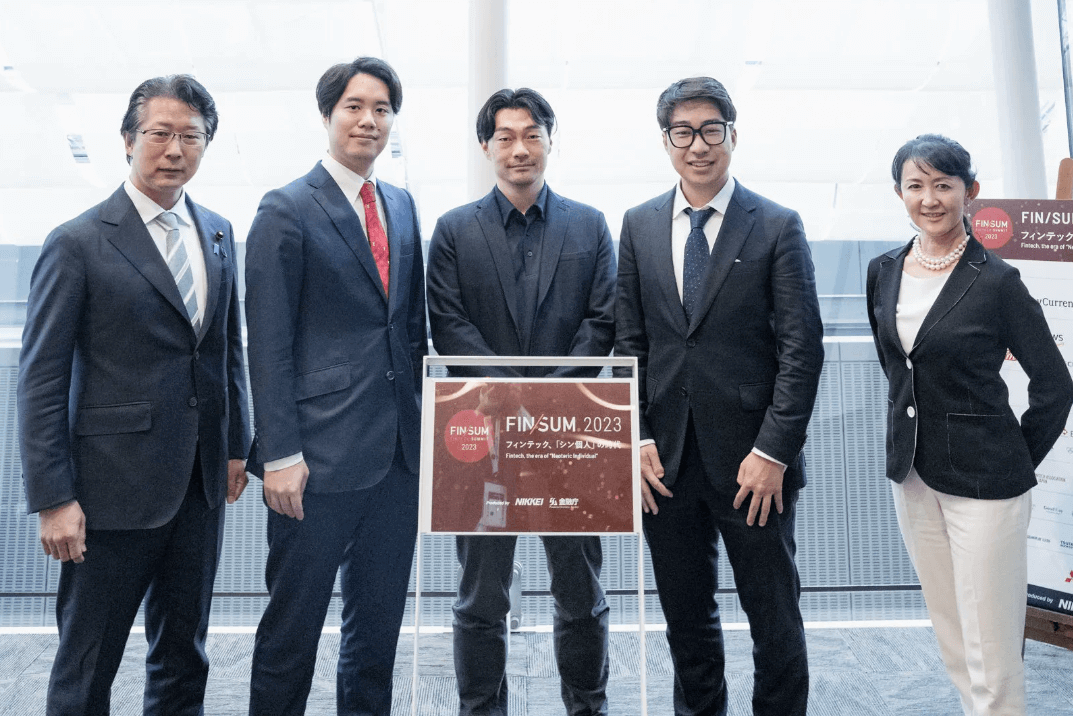【イベントレポート】FIN/SUM2023 シンポジウム「Web3ブレイクスルー!その実現に必要なものは何か?」
株式会社Ginco

概要
2023年3月28日から31日の4日間、金融庁&日経新聞主催のフィンテックカンファレンスFIN/SUM2023が開催されました。今回は『Web3ブレイクスルー!その実現に必要なものは何か?』と題したパネルディスカッションの内容をダイジェストしてレポートさせていただきます。ディスカッション後に運営参加者ともに口を揃えて「抜群に面白かった」という感想が登場した注目の本編、ぜひ最後までご覧ください。
登壇者のご紹介

- 衆議院議員 神田 潤一 様
- Astar Networkファウンダー 渡辺 創太 様
- G.U.Technologies 代表取締役CTO 近藤 秀和 様
- 株式会社Ginco 森川 夢佑斗
- バンキング・アンド・キャピタル 小川 恵子 様(モデレーター)
小川氏:本日は「Web3のブレイクスルー」をテーマに、どこに日本の成長を期待できるか、Web2やWeb3の議論の先に見えてくるものは何かについて、各界でご活躍されている方々とお話を交えて参ります。
神田氏:私は衆議院議員を務めております。20年ほど日銀に務め、その間金融庁に2年出向、フィンテック担当として2016年のFINSUMの第1回目の主担当として進めていました。その後マネーフォワードで4年くらい地銀さんたちとお仕事をし、1年半前に青森二区から出馬し当選させていただきました。今は経済、金融、スタートアップ、地方創生などに力を入れております。
昨年は1年間Web3関連で色々なことに取り組みました。去年1月に自民党のデジタル社会推進本部でNFT政策検討プロジェクトチームを立ち上げて、3ヶ月後にホワイトペーパーを公表しました。その後Web3を国家戦略にすると宣言し、4月の自民党の「デジタルジャパン2022」にそれが組み込まれ、6月の政府「骨太の方針」ではWeb3に向けた環境整備の検討を進めてきました。去年末には税制改正で自社発行トークンの時価評価の見直しが採用されるなど、Web3施策の成果が出始めています。今年は来月にWeb3のホワイトペーパーを公表する予定ですので、さらにこの一年で日本を進めていくぞ、ということを宣言して今進めているところです。
森川氏:株式社会Gincoの代表取締役の森川です。FINSUMには以前から何度か登壇してきましたが、今回が一番Web3を取り上げられる回だと思って楽しみにしてきました。私は京都大学法学部在籍時の「Web3」という言葉がない頃にブロックチェーンに携わり始め、もう8年程この領域にいます。2017年にGincoを創業して、企業様のブロックチェーンの活用、Web3領域への進出を支援してまいりました。ご縁をいただきブロックチェーンやNFTの入門書も執筆しております。
今回のFINSUMは今までと違い、遂にブロックチェーンの具体的なユースケースに触れられるフェーズになっていきました。一般の方には日常的にブロックチェーンに触れる実感はまだありませんが、ユースケースがどんどん創出され、これは素晴らしい体験だ、と実感する機会が増えていくことと思います。
今後ブロックチェーンの上に成り立つデジタルアセットがWeb3のユースケースの中心になっていきますので、これには技術的なハードルに直面すると思います。技術面のハードルとユースケースなどのビジネス面でのハードル、その2つの課題を自社だけで抱えていくのは大変ですので、我々がハブになって企業様の事業創出、事業価値を創造のパートナーとして一緒に作り上げていければと思っています。お陰様でGincoはプロダクトの導入実績で国内トップに引き上げいただき、金融機関様含め大手企業様をお取引先として尽力させて頂いております。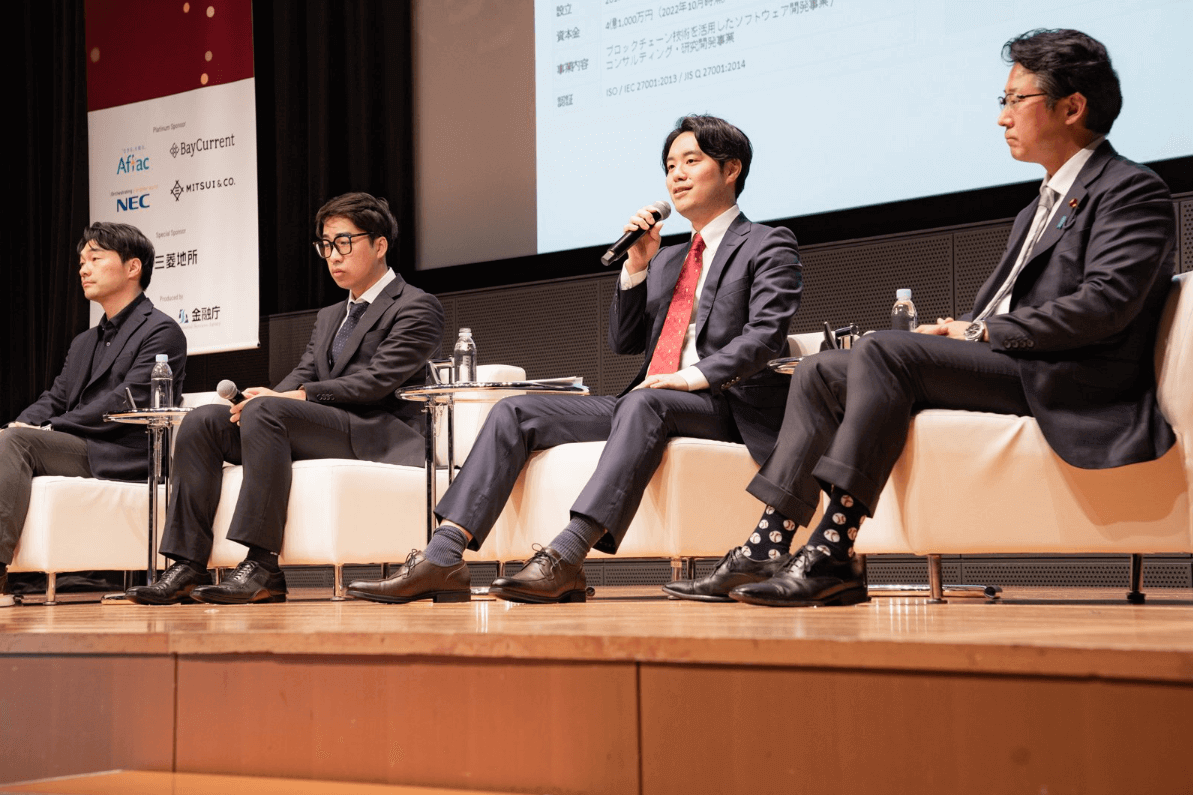
渡辺氏:日本初のパブリックブロックチェーン「アスターネットワーク」を作っている渡辺創太と申します。今インターネットを使う時にどこのサーバーに繋いでいるかを皆気にしていないと思います。しかしブロックチェーン業界は今たくさんのチェーンが乱立し「どこのブロックチェーンに接続して使っているか」を気にしながら使っている段階です。将来的にはこのブロックチェーンが繋がってインフラが整ってくる世界観の中で、私たちのチェーンがそのハブになりたい。Web2で言えばApple Store、Google Storeのように分散型のアプリケーションを作るためのスマートコントラクトのプラットフォームとして、本日はアスターネットワークを覚えていただければと思います。
アスターネットワークは国内外の投資家の方にバックアップを頂き、コインベースやバイナンス、ポリチェーンというアメリカの有名VCにも支援をいただいております。また、このWeb3という言葉を作ったギャビン・ウッド氏からも出資を受けています。日本でのNFTのユースケースとして「左利きのエレン」という漫画や、カルビーさんがNFTを配るための実証実験、トヨタさんとご一緒しているWeb3ハッカソン、ソニーネットワークコミュニケーションズさんとのインキュベーションプログラム、NTTdocomoさんとの地方創生のユースケース創出、博報堂さんとジョイントベンチャー、電通さんやGMOさんのアドバイザーなどをやらせていただいております。
アスター自体は今世界に22カ国に50人ぐらいのメンバーがいますが「今年は日本の年だ」と思っているので、日本のWeb3を力強く推進していけるよう、官民で力を合わせてやっていきたいと思っています。
近藤氏:G.U.テクノロジーズの近藤です。弊社はできて2年強、40名程のスタートアップです。元々私はウェブブラウザを作っていたキャリアがあり、その後ソニーで認証システムや決済の研究をして今の事業に至ります。ブロックチェーン領域はインターネット、決済、コンピューティングなどを含めた、ものすごく革命的な領域だと考えて会社を作りました。ソニーでは当時電子マネーが当たり前ではなかった時代に、フェリカ技術の研究をしていましたが、今後はこのWeb3の世界でさらに新しい革命が起きると考えています。
我々が扱っているソリューションは主に3つあり、1つは「Japan Open Chain」という、ビジネス領域で使いやすいブロックチェーンを立ち上げています。これは世界的に有名なイーサリアムにネットワークの遅さ、手数料の高さ、法的な安全性が分からない、という課題がある、という声を受けて皆で使いやすいものを作ろうとして立ち上げたものです。
もう1つ、ウォレット技術も提供しております。このWeb3の世界はまだ発展途上であり、新しい方が入るにはハードルが高すぎる点が課題に挙げられています。特に「メタマスク」という有名なウォレットがありますが、これを自分の親世代に使ってもらうにはかなり難しい状況があります。それを改善して世界に広めていきたいと考えております。
なお「Japan Open Chain」はNTTコミュニケーションズさんもご参加いただき、信頼できる21社の企業でやっていく方針で進めております。先日は日経新聞さんに取り上げていただき、金融機関さんとステーブコイン発行の実証実験を開始しております。このステーブルコインがWeb3の世界において非常に重要で、これが広まるか否かが業界の鍵になっていると考えています。日本がこの領域で世界のトップランナーになりつつあり、政府の方々の努力のおかげでコインデスクのような世界のメディアからも取材を頂き注目されています。それからもう1つ、ブラウザなどのユーザビリティのレイヤーも企業の方々と研究しながら開発を進めております。
Web3 日本のチャンスおよび課題は?
小川氏:では本題に入ります。先ほど近藤さんからステーブルコインが日本で進み、すでに手数料が少なく早く送金できるなどのメリットが広がっていますが、その次のフェーズとして例えばファンディングや新しい保険、NFTのデジタルアセット、現物資産と結び付いて広がっていくと見られていますが、この流れの中で実現されるWeb3の新たな世界を近藤さんはどうお考えでしょうか。
近藤氏:ステーブルコインについてはここ数ヶ月で特に注目されています。昨年のことですが、世界的に皆が使っていたLUNAというステーブルコインが一夜にして4兆円くらい失われた事件がありました。また、先日破綻したシリコンバレー銀行に通貨のエクスポージャーを持っていた世界的に有名なステーブルコインのUSDCが、一時ドルペッグ外れ、つまり、1ドルの価値があるコインが1ドルでは無くなった、というのが大きな話題になりました。これについてはアメリカ政府が保証することになって、今はUSDCは価格を取り戻している状況にあります。
そのような状況にありながらも世界的にはこのステーブルコインはすでに実際に使われている状況であり、例えば海外で我々がエンジニアを雇おうとすると、「支払いはUSDCでいいですか」と言われることがありまして、こちらの世界ではむしろ銀行口座は使われなくなりつつあります。今後日本でも給与払いなどでステーブルコインが解禁されていきながら、おそらく5年から10年後には普通に使っている世界になると思っています。一方で例えば、PayPayさんのような店頭決済での用途については、まだそこまでではないと考えております。なぜかというとブロックチェーンには弱点がありトランザクションのスピードがそこまで出ないからです。もう少し大きな単位のもので、例えばNFTでゴルフ会員権の売買、不動産売買、投資などに使われていく点で使い勝手が良くなるものと考えております。
小川氏:ありがとうございます。一方で先ほど渡辺さんがアスターネットワークでメンバーをグローバルに揃えている、という話がありました。多国籍でタイムゾーンも世界規模となるためビジネスの拡張性が違ってくると思いますが、そのあたりのお話をお聞かせください。
渡辺氏:私たちのメンバーは22ヵ国にいて、しかも皆がオンラインで作業しているため、国境を考えることなく昼夜が逆転して非常に大変なところがあります。経営スタイルも従来とはちがい、グローバルにお金があるところから資金調達して、たくさんいるところからエンジニアを採用して、ユースケースを作りやすいところから作る戦略を取っています。
今ちょうどアメリカではFTXの問題によって規制が強化されていますが、一方日本は4月に行われる「ETH TOKYO」というイベントに際して、海外の業界のトップの人たちが日本の状況に興味を持って多くの人たちが来日する予定です。
日本をはじめアジアがやっとWeb3の最先端になる番が回ってきた、というのが現状のステータスです。香港では最近中国人の方々がクリプトのハブにする、ということが言われ出していますし、一方でシンガポールは元々中国からの移民によって財源を確保できたため、カッティングウェッジのようなWeb3に張らなければいけないインセンティブが今は無くなっています。しかも国家ファンド「テマセク」がFTXに投資していたり、破綻したスリーアローズキャピタルがシンガポールに籍を置いたりしたこともあり、少しネガティブになってきています。
ただ、日本はというと、政治家の方々や省庁の方々が良いフレームワークを作り国家戦略にも入ったことで、ここから巻き返しが図れる、という見通しがあります。ただ、良い枠組みがあるだけでは世界のトップには立てないので、今は我々アスターもまだ世界で100位前後であるところを、今後世界20位、10位に入っていくようなプロダクトを作っていかないといけないと思っています。
小川氏:ありがとうございます。森川さんはWeb3のブレイクスルーの実現に向けて課題を何か感じられていますか。
森川氏:先ほど話題にあったとおり、日本は先に波乱がありその教訓から今回は比較的無傷でした。今は外部環境や制度設計においても非常にサポーティブな形に動いているためスタートアップとしては大変喜ばしい環境になっていると思います。一方で課題についてですが、日本ではエンタープライズの企業が良い意味で力を持っているのが特徴ですが、Web3がマスアダプションしているかと言えば「NO」の段階です。ここは大企業がけん引するところで、果たす役割は大きいと思います。これについては大企業や金融機関の方々がご認識されているがゆえに今回のイベントで積極的に情報交換やディスカッションに参加しているかと思います。
Web3の成り立ちを振り返ると、元々ビットコインというのはサトシナカモトという人物が0から100まで作り上げて成長させてきた、というわけではなく、色々なステークホルダーが力を合わせて対等な立場で推進していった点が重要かと思っています。日本はルールメイクの面でそれが成り立ちつつありますが、一方でビジネスの面ではどうかというと、若干距離がまだあるかと思います。というのも、ビジネスにおいては会社各々が「自分たちはこうする」「相手にこれは知られたくない」となってしまいがちです。
これは有志で成り立ってきたブロックチェーンやWeb3とは遠いところにあるもので、ブロックチェーンという共通のデータベースでデータを流通させることで初めてエンドユーザーや企業にメリットが生まれてくることから考えると、データも人もサイロ化すると良いものは生まれづらいかと思っています。「あちらの事情は分からない」「情報交換はしない」となってしまうと、これは課題になると思います。
Web3やブロックチェーンを掲げるからには価値の「協奏」を見据えるべきで、これは「競争」ではありません。共にクリエーションしていくという概念が一番重要で、大企業とスタートアップ、政府等も皆がフラットに議論をして、ビジネスの現場においても手を取り合うべきだと考えております。
小川氏:ありがとうございます。近藤さんは企業家としてWeb3への向き合い方や課題についてどうお考えでしょうか。
近藤氏:私はWeb1の時代から企業家をやってきましたが、20年前当時のウェブブラウザを作った頃が大変でした。日本では信じられないことに検索エンジンやウェブブラウザを作ると、当時は著作権法違反になってしまいました。違法ではないことを説明するのが大変で、次にこれをどうやってビジネスにするかで悩みました。いつかネットのバナー広告で車が売れるようになる、という夢を皆で語っていましたが当時は誰も信じませんでした。今それを信じない方はいなくなっていますが、日本はそこから学んだことで今政府の方が本当に協力的になっています。これは驚くべきことです。
アメリカの話を聞くと、政府が結構バラバラでうまく強調できてない話も聞きますので本当にチャンスだと思います。起業の文化が整えばWeb3は日本が勝てると思っておりますので、皆が参入してほしいです。
渡辺氏:森川さんが先ほどすごい良い点を仰っていて、今Web3に対する取り組みは大企業の皆さんが進めていますが、特にこの半年間が最も重要だと思っています。来年になってしまうと色々なプロダクトが出てきて各社ポジションを取ってしまうと思いますが、すると「この会社はこれをやっているから私たちと競合だ」みたいな話になってしまうと思います。今はまだプランニングの段階、プロダクトを出してない状態なので、このタイミングから情報をどんどんシェアして、お互いにできることはやっておいた方がいいと思っています。例えばウォレットが乱立した時に、例えば「KDDI✖Docomo」のようなことをやるタイミングではないと思います。グローバルで覇権取れるか、という話をしなければいけない中で、日本のマーケットという観点ではなく、メタマスクの上位互換を作るためにはどうやっていけばいいか、という点で頭を使うべきかと思います。
神田氏:私は制度を作る立場を務めてから、その後に暗号資産取引所の立ち上げに携わりましたが、以前の取引所の流出事故などがあって規制が厳しくなりそれが失敗に終わりました。今ルールメイカーをしておりまして、この3つの立場をここ7、8年でやってきていますが、この立場から今は2つのことを考えています。
1つは、日本はルールが決められていないグレーな世界に皆出ていかない傾向があること。海外はそこが主戦場であって、規制される前にどれだけ自由にビジネスを作れるか。皆でチャレンジしてどんどんリスクを取っていくわけですが、日本は「ここまでいいですよ」と言われないとグレーな世界には出ていきません。それで海外に遅れてしまうわけです。まさにかつての暗号資産と今回のWeb3が同じ状況で、そのグレーなところについて「ここまで大丈夫です」をはっきりさせて安心してビジネスを作ってもらう、ということを心がけています。今まで日本がなぜそんなに規制作りをアグレッシブにやっているのかと世界と比較されますが、日本は規制を作らないと皆そこに出ていかないから、という理由があったわけでした。
またもう1つ、FTXの件で海外は今かなり規制を厳しくする流れになっていますが、日本はまさに暗号資産でかつて経験したことを生かしたことでそれほど被害が出ていません。それは分別管理をしっかりやってきたことがメリットになっていました。やはりこういう厳しい時こそやるべきことをやっていくのが大事なことで、厳しい嵐の中でもしっかり根を張って規制を作っていくと、やがて開けてさらに成長するマーケットになった時にどんどん伸びていけるのではないかと思います。今は苦しい時ですがここが頑張りどころと思って規制を作っていますが、この間にコンテンツやビジネスを作っていただきたい、というのが我々ルールメイカーの立場としての思いです。
小川氏:ありがとうございます。おそらく日本は国家としての強みが特徴だと思います。数年前にこのFINSUMで『リギュレトリーハッキング』という著作の紹介がありましたが、パワーバランスの中でルールメイカーといかに組んでいくか。それが競争力を育てていく、という内容でしたが、今では日本がこの点で世界に先駆けている、と心強く思っております。
Web3でリアルアセットがブロックチェーンにのると、どう世界はスケールするのか?
小川氏:では、次のテーマではアセットがブロックチェーンと繋がっていくとどういったことが起きるのか。先ほどジャガイモのNFTの話もありましたが、渡辺さんから話をお聞かせください。
渡辺氏:ビットコインのそもそもの成り立ちが既存金融に対するアンチテーゼ的な側面を持っているため、クリプトアセットとリアルアセットが今まで離れていたのは、腑に落ちる部分かと思います。リアルアセットをブロックチェーンに紐づけていくことはWeb3がここ数十億人に使われるようになれば間違いなく起こることです。例えばテスラの株式などがブロックチェーン上で取引できるようになれば、それこそ24時間365日取引ができるわけです。全体的なメンテナンスコストも安くなります。
すでにやっているNFTの事例で言うと、カルビーさんの事例では、カルビーのポテトチップスは日本で数千万人の人たちが確実に食べたことがあるかと思いますが、買う場所が例えばコンビニであったりします。しかしこれではカルビーさんとしては誰が買っているかがわからない。現金で決済した場合に誰かはわかりませんし、この商品の愛好家が誰なのかが見分けがつきません。そこでアスターのエコシステムで行った実証実験では、 アスタートークンをステーキングすることでジャガイモのNFTを作った人がそのNFTとカルビーの商品を交換して受け取ることができる、ということをやりました。こうするとアスタートークンをわざわざ買ってステーキングしてくれて、かつジャガイモのNFTを作る人というのは確実にカルビーが大好きな人として断定できます。
そして例えば、その方々の住所や年齢、どのような経緯でこのプロダクトを知ったのか、などアンケートに回答してもらう。このようにNFTを通して新しいカスタマーエンゲージメントに結び付けられるのではと思います。この方法は日本経済では車などと相性が良いと思っています。 今まさに既存企業がWeb3に入ってユースケースを作っていますので大きな進展になると期待しています。
小川氏:ありがとうございます。神田先生は地方再生の分野にも力を入れているとのことですが、ブロックチェーンで民主化・分散化を目指す自律分散型組織やDAOなどのガバナンスをどうすればよいかという課題、またそこから生まれる期待についてお話いただけますでしょうか。
神田氏:いま自律分散型組織、DAOが注目されてますが、Web3でいったい何ができるのかというと、デジタルコンテンツが流通すること以外にも、Web3を使った町興しや地方活性化も政府としては大きな目的にあります。その推進母体としてDAOが注目されておりまして、実際に新潟県の山古志地区や北海道の与市町、岩手県の紫波町、ガイアックスの「美しい村DAO」を立ち上げて、地域の良さをNFTやトークンを発行しながら発信しています。そして、そのプロジェクトをDAOで回して進めていますが、これまでの株式会社、ボランティアやNPOとも違う新しい地域やコミュニティの作り方が登場しています。これがうまくいけば世界にもどんどん発信できますし、少子高齢化や課題の多い地域にとってコミュニティの再生に繋がっていきます。今ホワイトペーパーを作っていますが、DAOの課題を整備してDAOの法制化を自民党として進めていこうと考えています。
小川氏:ありがとうございます。リアルアセットというと不動産などの議論がすでに始まってますが、一方で社会課題の解決という側面で少しご意見をお聞きしたいと思います。貧困問題等々の社会課題は難しいテーマですが、そこにWeb3という潮流がどういった貢献をしていくのか、という点で近藤さんからご意見をいただけますでしょうか。
近藤氏:Web1とWeb2は情報革命と言われますが、Web3では金融革命、つまり金融の民主化が起こっています。情報革命では今までマスメディアしか流せなかった一方的な情報を双方向に流せる世界になったわけですが、Web3では例えば、地方にいる人が面白いことを考えてYoutubeで発信すれば世界中からお金を集めることができます。つまり個が持っている力を最大限に発揮することで、世界中で1人でも共感してもらえればお金が世界から集まってきます。
日本人は銀行口座を皆が持っていますが、アフリカのある国ではほとんど持っていません。その方と取引したい場合、ウォレットさえ持っていれば送金ができるようになる。これが金融システムの上で今動いているパラダイムシフトです。
NFTはDID(分散認証)という、今あるようなGoogleさんやマイクロソフトさんのIDではなく、世界中の誰もがIDを認識することでその人に対して何かアクションが起こせるようになります。このウォレットとDIDの2つが組み合わさることで新しい変化が期待できます。
Japan Open Chainの「e-加賀市民制度」では石川県でNFTを配布していますが、加賀市が認証した方に対して別の企業が何かを付与する、などのサービスを提供できるようになっています。
このようにお金がものすごく流動化すると最終的に貧困問題の解決に繋がります。今後AIが登場して10年後には私たちの職業がなくなると言われていますが、個々が自分のユニークな個性を発揮し世界の誰かがそれを発見してくれれば、ひいては問題が解決していくと考えています。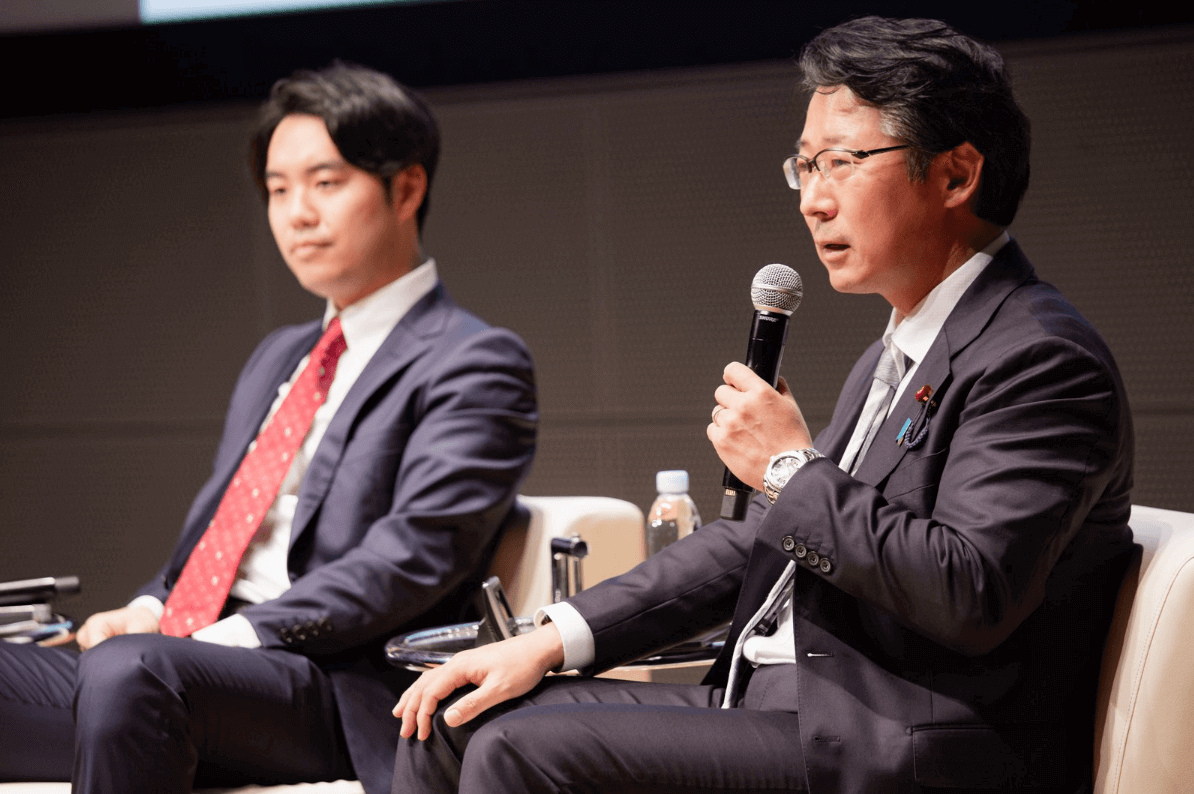
小川氏:ありがとうございます。特に日本は少子高齢化、社会保障などが重い社会問題になっていますが、すでにブロックチェーンを使って見えなかった価値を可視化して分配していくなどのチャレンジもあると聞いています。森川さんはこういった分野の社会課題に対してWeb3にどんなものを期待されていますでしょうか。
森川氏:難しい質問なのでレイヤーを分けてお話しますが、まずブロックチェーンのメリットは何なのかについて考えてみると、1つはデータを可視化することだと思います。先ほどのジャガイモ好きの人のデータが「見える化」されていました。もう1つのメリットは行動に対してのフィードバックがあることだと思います。資本主義においては「通貨をもらえる=良い仕事や行動」と必ずしも直結するわけではありませんが、相対的に判断されるものがあるわけです。その価値判断軸を新たにいくつも立てていけることがWeb3ならではの面白い概念だと思います。
そのためにも、先ほど近藤さんの仰ったようにユニークな点を見つけていくことが大事です。 資本主義では1本の価値判断軸では評価できない行動も、いろんな価値判断軸を作ることで評価されやすくなり、対価が支払われる仕組みが生まれる。これがWeb3のトケノミクスと言われる世界と考えることができます。
そこで高齢化や社会保障、地域の話や社会課題についての質問に戻ると、今の枠組みでは金銭的にリターンが小さいものも、別の形があることでより多くのリターンが得られる。それによって行動に移そうとする人が増えるかもしれません。そしてよくDAOやNFTの話が出てきてあまりピンと来ない人も多いかもしれませんが、これについては例えば私が小さいころに募金してもらった「緑の羽」なんかを思い出します。これと同じように何かをやった証が欲しい、という気持ちは多くの人の根源にあるのではないかと思います。このようにNFTを証として持つことで可視化されて行動が変わる、というのは意外と価値ある行動に結び付くのではないかと思うわけです。このような小さな事例ですが、企業や行政の手が届きにくい身近な課題を解決するためにWeb3は何かしらの手立てを提供できるものだと考えております。
小川氏:ありがとうございます。また、日本国の強みとしてアニメなどのデジタルアセットがあると言われていますが、神田先生はこれについて国家としていかがお考えですか?
神田氏:日本では「クールジャパン」という形でコンテンツを海外に広めていく取り組みがありました。私もテレビが好きで、アニメの世界、ゲームの世界に浸って育ってきました。ですので、仮想通貨が出てきた時に自然とそれを受け入れ、Web3の世界もゲームの世界に自分が入ることができる、という感覚を持った人もいたかと思います。我々が慣れ親しんできた世界について海外の方も、日本的な世界観がインターネットの世界に広がっている、とイメージする人もいるのではと思います。
ゲームの世界観や日本のコンテンツというのは、それだけで世界にアピールできて日本にとってチャンスになっています。このクールジャパンの取り組みの延長線にWeb3があると私たちは捉えていますので、この観点からも政府としては後押ししていきたいと考えています。
Web3で個人を主役と考えたときに何が変わっていくのか?
小川氏:ありがとうございます。最後に今日の表題の「シン個人の時代」についてWeb3で今後変わっていくことへの期待、面白さについて一言ずつお聞きします。
近藤氏:例えばYoutuberというのは5年くらい前には想像できなかった職業で、少し前は良く思われていなかったにも関わらずいつの間にか1億円プレイヤー、億り人になって羨ましい対象になっているわけです。これが「小学生がなりたい職業1位」になっている状況について、今後はWeb2の時代で実現したことがWeb3でもさらに広がると考えています。誰もが起業するようになって、「起業する」という言葉が死語になってしまうくらいの世界が来る、というのが私の願望です。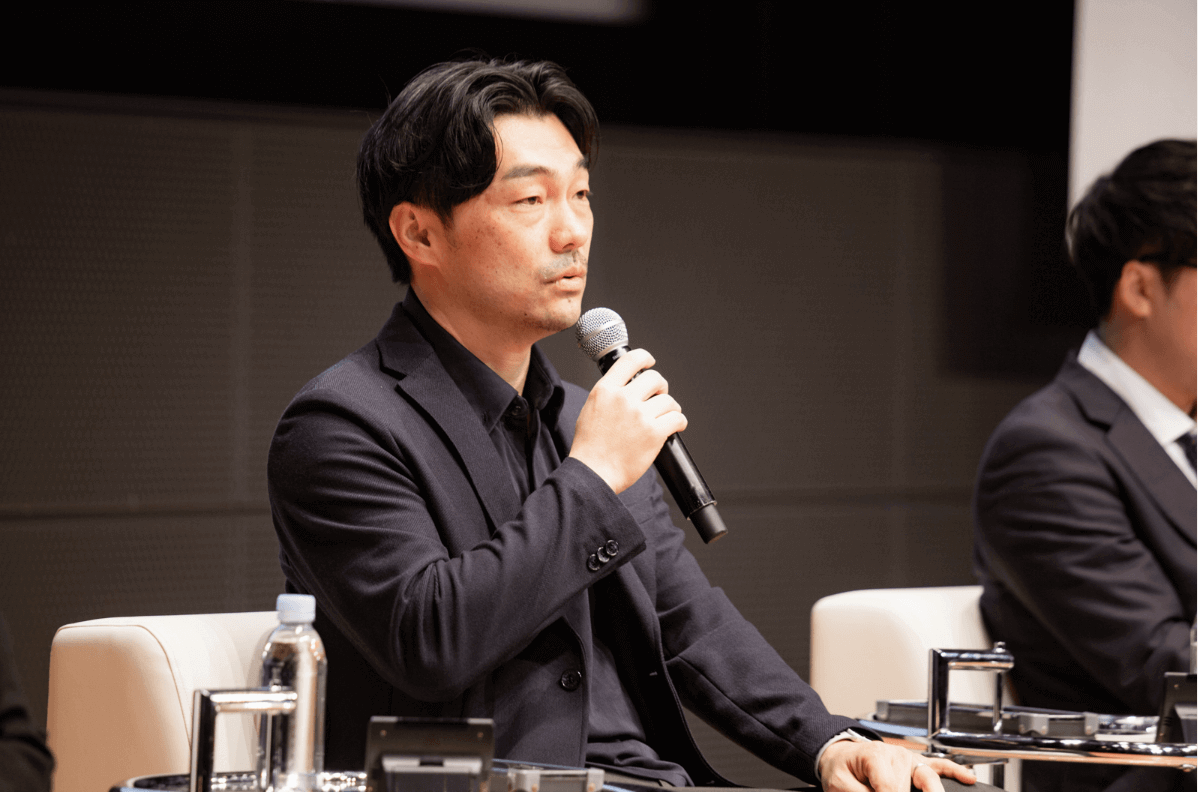
渡辺氏:ここに来られている方は大企業の方々が多いかと思いますのでそれを後押しできることをお話させていただきます。よく「Decentralization(非中央集権化)」と言われますが、あれは「分権化」がおそらく正しい訳であって、つまり誰も中央集権的なことは否定していません。例えばブロックチェーンのノードを立てなければいけない、となると今でもだいたいがMicrosoft AzureやAWSなど、いわゆるWeb2のサービスで成り立っています。暗号資産を持ったり買ったりするのは取引所で、自分の資産をウォレットやハードウェアウォレットで管理している人は稀だと思います。要するに今のインターネットは企業主体のインターネットになっていて、重要なのはユーザーが自分で選べるようになることだと思います。まだ個人が選べるようにはなっていませんので、そこを個人中心のインターネットにしていくことがWeb3の本質的な部分だと思います。
中央集権的なサービスがあってもいいとは思いますが、大企業の皆さんも大企業ならではの自分たちの確固たるポジションを築いていくために既存のアセットを生かしつつ、一方でWeb3のドメインやウォレット、ノードのプロバイダーやインデックシングなどのドメインがあるので、そこを選んで使っていただきたいと思っています。
森川氏:今まさに渡辺さんの素晴らしい話がありましたが、今は個人か企業か、「toB」か「toC」か、を問うような枠組みではもはやなくなってきています。選択肢が増えるということは個人にはとても良いことですが、企業からすると非常に危機感があることです。自分たちが選ばれないかもしれない、という話になっていきますし、企業に就職せずにDAOに就職する、むしろ就職という概念自体が古くなるかもしれません。今度はDAOと人材獲得争いになるかもしれないわけです。
そうなると、企業は今までよりスピーディーに新しいことを仕掛け、自分たちのポジションを考えなければいけなくなります。すでにWeb3をやるかやらないかという問題ではなく、個人の動きは本当に早いので、それに対して企業も私もどう向き合っていくか、そういうことをここにお集まりの方と皆で考えて、手を取り合ってどうしていくか。結果としてこの「シン個人」の人たちがどれだけベネフィットを受けていくかを、一緒に考えて盛り上げていく必要があると思っております。
神田氏:私はこれからはプラットフォーマーに束縛・管理されずに自分たちで色々なコンテンツを発信していける、しかもそこから収益を取っていけるという時代になっていくと見ています。その中で大事なことは、著作権や肖像権をしっかり確立した上でコンテンツを作った人に収益還元されていくような時代、あるいは誰かに搾取されないような時代になっていくと思いますので、我々はそのような環境を整備していきます。スピードが早ければ早いほど我々も一生懸命ついていきますので、安心して自由にコンテンツやプロダクトを世界に発信していってほしいと思っています。
小川氏:本日は皆様どうもありがとうございました。では、今日はこれで終了いたします。