【イベントレポート】Web3 Development MTG#1「これからのWeb3の話をしよう」
株式会社Ginco

概要
株式会社Gincoでは、Web3の普及と発展に向けて、「Web3 Development MTG」というイベントを開催しています。Web3の魅力と価値を周知する場になることを目指すこのイベントの記念すべき第一回では、「これからのWeb3の話をしよう」をテーマに業界の有識者として、double jump.tokyo株式会社の上野氏、株式会社メルカリ取締役の伏見氏、森・濱田松本法律事務所の増田氏を招き、Web3の未解決な課題と今後の展望についてパネルディスカッションを行いました。
このイベントレポートではその様子をコンパクトにまとめてお届けしていきたいと思います。
いまなぜWeb3なのか?
森川氏: 本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。今回お集まりいただいた御三方は、多種多様なバックグラウンドをおもちで、様々な専門領域・事業形態・事業規模な一方、Web3という共通の領域でビジネスモデルを構築しています。なので、様々な視点からお話を伺って、立体的にWeb3のお話を聞ければと思います。まずは、「なぜいまWeb3なのか」というところから伺えればと思いますが、上野さんどうでしょうか?
上野氏: Web3というと範囲が広いので、多種多様な切り口のもとでいろいろな意見を言えてしまうので、NFTを中心に話をしようと思います。DJTを設立したのが2018年で、2017年にCryptoKittesが誕生したのがきっかけ。ソーシャルゲームとかが登場してあらゆるものが無料で使われる感覚が強くなっていくなかで、資産としての価値をゲームの中心に持ってきたCryptoKittesに面白さを感じましたね。
サブスクリプションの普及によって今までは一つ一つ選んでいた音楽や動画などのコンテンツが、ある意味で大雑把に消費できるようになった。これによって、デジタル空間で「手触りのある価値を実感する」ということは難しくなっていて、そういったモノの受け皿のような役割をNFTが引き受けてくれると思ってます。デジタルなモノっていうのは、価値が元々あるのだけど、その価値が可視化されていなかった。それを可視化するための容れ物がNFTだと考えてます。
森川氏: なるほど。価値が可視化されるという話がありましたが、NFTが登場する前と後に決定的な違いというのはありましたか?
上野氏: ERC721のような共通仕様ができたのが大きいですね。開発者が共通する仕様で、「これが一番便利だからこれを使おう」と思えるのがすごく重要で、色々なエンジニアが色々な規格で作ってしまうと、業界が混乱してしまう。ベータ対VHSの論争を思い出します(笑)
森川氏: 確かに(笑)その点NFTはERC721があるから、どっちの規格が勝つかわからなくて参入しづらい、ということは無いですし、開発側としても参入しやすいですね。
伏見さんのところのメルカリ・メルコインではどのようにWeb3について捉えているんですか?動機も含めてお伺いしたいです。
伏見氏: メルカリはWeb2の象徴みたいな会社で、デジタルな空間で価値ある商品を相互に取引する、というプラットフォームを提供しています。そんな中で、デジタルネイティブなアセットが増えてきたな、という印象です。
Web3が盛り上がってくる中で、いつ参入を考えたかと言われると、実は結構前からタイミングを狙ってました。準備は前々からしていて、その結果として暗号資産交換業ライセンスもメルコイン設立から早いタイミングで取得できました。
森川氏: 既存の事業があるなかで、参入のタイミングを見計らうというのは、至難の業だと思います。具体的に何を契機に参入を決定したのかと、参入に向けて壁になったことがあればお願いします。
伏見氏: 個人のやり取りする価値の流通量・取引ボリュームが増えてきたタイミングで参入しようと決めてました。メルカリは上場企業のため、リスク評価が極めて難しく、チャンスがあっても流出などがあったら既存事業に多大な影響を与えてしまう等々、そういう議論が繰り広げられていて苦労しました。
ただ、GincoさんやDJTさんのように進出をサポートしてくれる企業さんがいると、とても頼もしい。みんなでエコシステムを作っていける世界観でタイミングとスピード感を大事にしたい。
森川氏: ありがとうございます。こういった壁=リスク評価は、考えるのは当然なのですが、そこで止まりすぎてしまうと、タイミングを逸してしまいます。そこのバランスが大事というのは、重要な論点だと思います。
増田先生に、初めてお会いしたのは、金融庁に出向されていた頃のことですよね。法律の専門家として、どのような意図でWeb3に参入しようと考えたのでしょうか?
増田氏: 私も上野さんと同じで、CryptoKittesが出た時ですね。ガワだけ変えれば幾らでも別のジャンル・キャラクターで同じようなゲームを作ることができるということに将来性を感じました。また、その結果としてコンテンツが取引可能になるという世界が一気に拡大する未来が想像できたことも大きかったですね。
森川氏: 法律関係で、増田先生にお伺いしたいのですが、規制はNFTのようなメディアの在り方にどのように影響するでしょうか?
増田氏: 日本の場合は、規制の影響でイノベーションにとりあえず待ったがかかり易い。リスクヘッジはもちろん重要だが、リターンとのバランスを考えるのがまずは重要だと思います。また、規制も重要ですが税制も同じくらい重要です。税制は人々の行動様式やビジネスのベクトルを大きく動かせるインセンティブ設計ツールです。ですから、税制をしっかりと形作っていく必要があります。
森川氏: 規制・税制の話になると、どの国が規制・税制で良いのか、という議論にもなりがちだと思いますが、この点は皆さんどうでしょうか
上野氏: かつてのアジアで金融拠点といえば上海、香港、東京、シンガポールでした。中国が規制をしたので東京とシンガポールが残るはずだったのが、東京は勝手に脱落した状況(笑)ただ、税制や規制で舵取りをしっかり行えば、東京は必ず復権し得ると思います。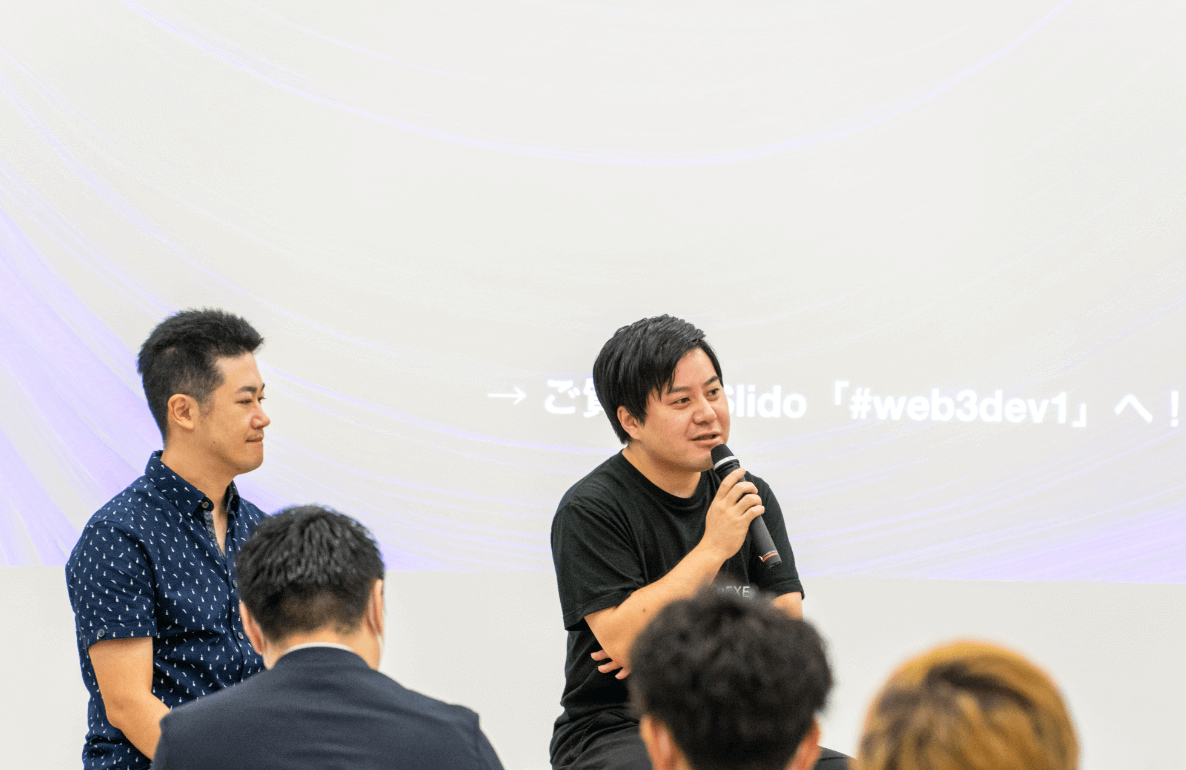
Web3に冬到来?これからどうなる?
森川氏: 昨今、暗号資産市場の暴落からWeb3に冬が到来したと言われています。そういったところの皆さんの肌感覚をお話いただきたいです。
上野氏: 冬といえば冬だけど、暖冬って感じ(笑)そもそも、ここにいるような人たちは雪国育ちなので、そこまで冬?っていう感覚だと思う(笑)2017年-18年の極寒の冬を体感している人たちからすればこのぐらいはまだまだ暖かい。
直近の夏=2021-22初頭まではマーケティング勝負のパリピバトルって感じだった。DJTもそうだけど、日本の会社、日本の企業ってそういうのが正直いってあんまり得意じゃない。なので、今の冬は実力というかコンテンツ勝負で、コンテンツを大事にしながら面白さを追求する必要があって、地力と実力が必要。だから、今の冬の方が日本の会社は過ごしやすいんじゃないかなと思います。
伏見氏: 上野さんのいう通り、冬=リセッションの時期はプロダクトの本質が見られると思います。マーケティングだけではもう生き残れなくて、NFTという技術をしっかり活かしたプロダクトの本質を突き詰め、ちゃんと面白く、ちゃんと便利、ちゃんと価値がある、より洗練されたものが出てくることに強い期待感があります。
森川氏: すごく共感できる。これからはマーケティングはもちろん大事だけど、プロダクトの本質と明確なユースケースが必要だと思います。一方で、メルカリのような上場企業だと冬の時期に参入するのは株式市場から不安の声もあると思います。その点はどのように向き合っているのでしょうか?
伏見氏: 弊社はプロ野球と手を組んでいて、まだまだマーケットとの温度感を探っている段階なのですが、プロダクトを磨きこめるという手応えがあります。例えば、始球式の権利を紐付けたNFTは大反響。NFTはよくわからないけど、始球式で投げたい!という思いは相場は関係ない。そういったプロダクトの本質を大事にしていけば、マスアダプションへのキャズムは越えられるんじゃないかなと思っています。
増田氏: 皆様のおっしゃる通り、私も暖冬だと思っています。17年、18年に比べれば、全然まだまだ。法律相談も引きも切らぬで全く衰えていない。また、規制は悪者にされがちですが、競争のルールを整えて、促進のきっかけになるでしょう。米国でも今後規制が明確化されていくので、ここから大きなプレイヤーの参入が期待できると思います。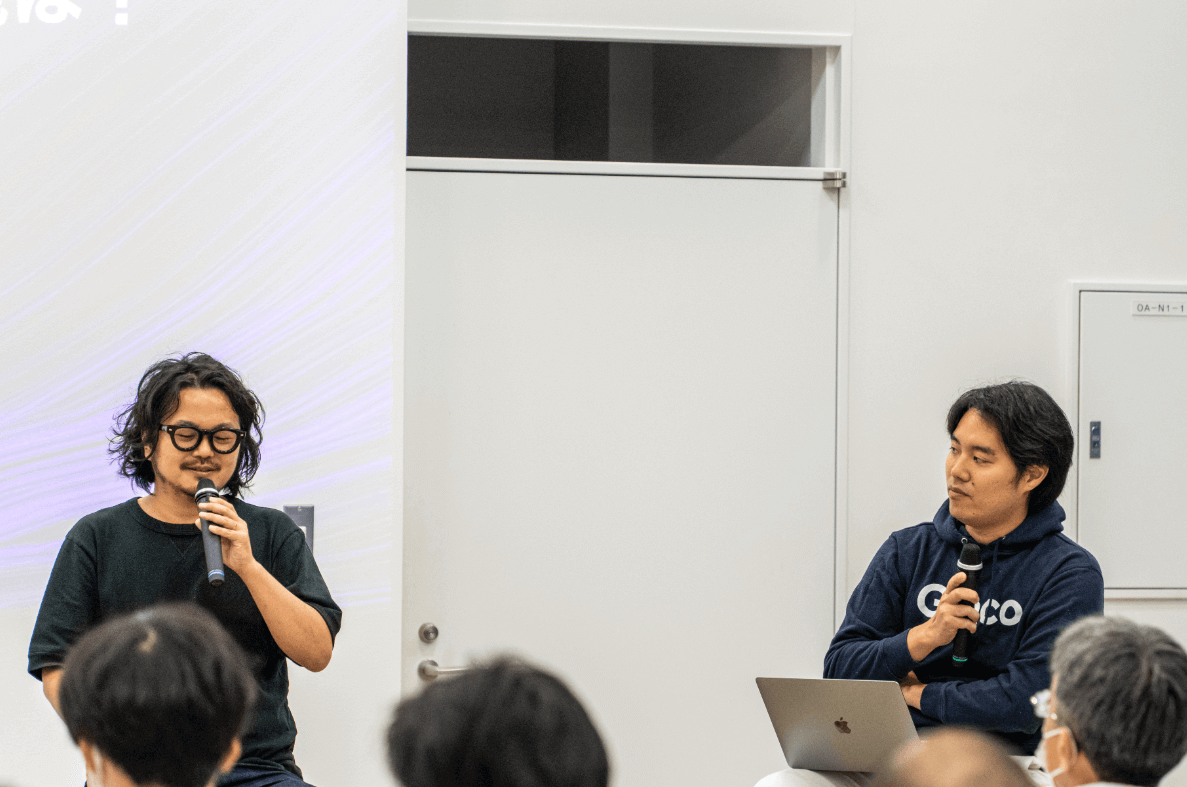
Web3の社会実装に向けて今解決すべき課題は?
森川氏: 最後のテーマですが、業界で気になる課題とそれをどう改善していくのかお聞かせ願いたいです。
増田氏: UI/UXがまだまだ追いついてないのかなと感じています。上野さんはどう考えてますでしょうか?
上野氏: 増田さんの意見はおっしゃる通りで、DJTとしても業界としても改善していないといけないと課題感を持っています。ただ、幸いにもゲームユーザーはリテラシーが高くて、その点試行錯誤できるのがありがたいです。
伏見氏: とはいえ、じゃあ今銀行口座のUI/UXが理想的かと言われれば、多分そうじゃない。例えば、NOT A HOTELの事例などでは、ウォレットの事なんて知らなくても権利に惹かれて買う人がいますよね。先ほどの始球式の例も同様ですが、UI/UXが整っていなくても必要性や魅力がその壁を超える場合もあると思っています。とはいえ、 UI/UXは重要なのでメルカリでもウォレットをガッツリ意識させるプロダクトは違うよね、という感覚はあります。上がり方は一つじゃないと思いますし、ぶっちゃけて言うとメタマスク等の既存のサービスに頑張ってもらいたい(笑)
上野氏: ファンや顧客にこれまでにない体験だったり、革新的な価値を感じてもらうサービスを追求するのも大切だが、そうしてNFTを買った人がUI/UXで不幸な気持ちになるのは避けないといけないですね。
増田氏: 究極的には誰も意識せずに利用できるような状態が理想だと思っていて、そういうUI/UXを実現するのがどこなのかな、と注目しています。ステーブルコインなどの世界ではもともと生活者の財布を預かっている金融機関が勝つはずだ!と金融機関は言っています(笑)
伏見氏: 給与のデジタル払いの規制などもWeb3への追い風だと感じていて、デジタルで身近なウォレットにデジタルなマネーが流入しやすくなるんじゃないかなと考えています。資本市場の温度感だけで考えるのではなく、成熟度や社会の風向き、活気で考えるとむしろ春なんじゃないかと考えています。
Q&A
Q:共通仕様とは言ったもののERC3525やERC1155など複数ありますが、全てを包含したスマートコントラクトは出るのでしょうか?
上野氏: 多分そうはならないと思います。標準規格というのはルールではなく、実態が作るものです。みんなに使われるユースケースが規格となっていく。ユースケースは漸進的に変化していくのではないかなと思います
Q:NOT A HOTEL のような不動産やまた、Unicaskのウィスキー等動産に紐づいた、リアルアセットをBlockchainやNFTにしたソリューションについてどのように考えられてますか?
伏見氏: NOT A HOTELの区分所有事例はとても面白いと思います。利回りに見えるとSTに近づいてしまうので、避け方が上手いですね。誰かが避けて大丈夫だった所から規制がアジャストされていくようになるのではないかな
Q:トークン活用とポイントエコノミーはどう違う?
上野氏: あらゆる市場において、パイが大きくならないと奪いあいが起こると思います。ゲーム業界においてWeb3の価値はインベスターなどこれまでいなかった参加者が現れパイが増えることにあってそれだけでもうハッピー(笑)。共通化が進むのでコラボレーションがしやすくなるのも利点です。ブロックチェーン=コラボ基盤と捉えるとビジネスマンにも意義が伝わりますし、匿名のインフルエンサーともコラボできると思います。
伏見氏: メルカリポイントをトークン化するかといったらしないです。なぜかと言われれば、メルカリポイントはサービスをグロースするために最適化されていて、どこで発行しようがそこは変わらない。しかし、ESGなどと絡めてステークホルダーを巻き込むならトークンにする意味があります。つまり、トークンに適したデザインが必要です。
増田氏: ブロックチェーンじゃなくてもいいことを無理やりブロックチェーンにする意味はないと思います。ブロックチェーン上に乗せることで、他のサービスやステークホルダーとの相互関係が生じます、それを活かすことが大事。どっちが優れているとかの話ではなくて、どっちが適しているか、どう組み合わせるかが重要だと思います。
まとめ
今回のWeb3Development MTG Vol.1ではWeb3のこれからに向けて、三つの題材でパネルディスカッションを行いました。Web3というワードがトレンドになる以前から事業を行っていた御三方に、現状と未来に向けてどのような取り組み方が必要なのか、課題とそれを乗り越えるにはどうしたら良いのか、ということを伺うことができました。
また、「暗号資産の冬」と呼ばれる2022年秋において、この冬が暖冬なのか厳冬なのか、という肌感覚の話がありましたが、この冬を乗り越えられるのか、否かというのは、伏見氏の言っていた「プロダクトの本質」を企業が工夫によってどれだけユーザーに与えられるかが重要になるのではないかと思います。
また、弊社Gincoでは、ブロックチェーンの活用を検討されている企業様向けにブロックチェーン導入支援・コンサルティングサービス等を行なっております。もし、セミナー参加者様、本レポートをご覧になった方でご関心があれば、下記の弊社概要欄よりお問い合わせください。